勤怠管理の効率を上げるために、タイムカードの電子化を検討している担当の方へ。タイムカードから勤怠管理システムへの切り替えを検討するタイミングや、タイムカードを電子化するメリット・デメリットなどをご紹介します。
“勤怠管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
勤怠管理の電子化とは、従来の紙のタイムカードや出勤簿などを用いて行っていたアナログの出退勤管理を、PCやスマホなどのITを用いてデジタル化することを指します。単にExcelやメールなどを用いてデータ化するだけではなく、データ化を通じて勤怠管理業務を効率化することまで含むのが一般的です。
従来の勤怠管理では、タイムレコーダーにタイムカードを差して出勤・退勤を行うのが一般的です。しかし、その場合、総務スタッフが月末になったら各人のタイムカードを集めて回って、それぞれの勤務時間を算出しなければなりません。手間がかかるし、ミスが発生するおそれもあります。
勤怠管理システムを導入すると、業務は以下のように簡易化されます。
それ以外にも、「タイムカードを用意する手間・コストが省ける」「タイムカードを保管するスペースがいらない」「計算ミスをするリスクがなくなる」など、多くのメリットが期待できます。本記事では、タイムカードをデジタル化(勤怠管理を電子化)するメリットやデメリット、タイミングなどについてわかりやすく紹介します。
なお、アスピックではその他にも「勤怠管理システム比較16選」「勤怠管理アプリおすすめ15選」など勤怠管理システム・アプリの選定に役立つ記事を用意しています。「色んな角度で比較検討したい」「自社に合ったものを探している」という方は参考にしてください。
勤怠管理システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“勤怠管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
タイムカードの勤怠管理に限界を感じながらも、電子化のタイミングを掴みきれずにいる方もいるのではないでしょうか。電子化を検討するタイミングとしては、以下の4つが考えられます。
以下、一つずつどのような場合が当てはまるのか具体的に記載していきます。
2019年、労働基準法など働き方改革関連法が大幅に改正され、以下のような様々な義務が定められました。守られない場合、企業には「30万円以下の罰金」などの罰則を課される場合もあります。
企業がこれらを遵守するためには、各従業員の労働時間を正確に把握することが重要。従来のやり方では、「月末になってタイムカードを集計したら残業時間の上限オーバーしていた」という場合も少なくありません。もし、そういったケースがこれまで散見するようであれば、今後のリスク回避のためにも、タイムカードの電子化を検討するタイミングといえるでしょう。
支店・拠点の労働時間の集計や給与計算を本社で一括する場合、タイムカードの情報を集めるだけでも一苦労です。なかには、支店・拠点に管理者が不在で、タイムカードをそのまま本社に郵送しているケースもあるかもしれません。このような無駄の多い運用を見直すタイミングも、タイムカードの電子化検討に適しているでしょう。
コロナ禍が大きなきっかけとなり、テレワークやサテライトオフィスなど働く場は広がってきています。そうした新しい働き方に対して、旧態依然とした労務管理方法が追い付いていない可能性があります。
自宅やコワーキングスペースなどでのテレワーク、出向先への直行直帰など、多様な勤務形態を認める場合や、シフトの種類が増える場合などは、手作業の申請・集計が大きな負担に。そのため、多様な働き方を実現する際にあたって、タイムカードの電子化が欠かせません。勤務形態を見直すタイミングで検討してみるのも一手です。
残業、休日出勤、休暇などの申請を紙で行っていた場合、勤怠管理システムのワークフロー機能を利用するのがおすすめです。申請から承認までの流れを勤怠管理システム上で完結できるので、申請に関わる手間を大幅に削減できます。また、申請のために出社する必要もなくなるでしょう。
タイムカードの代わりに勤怠管理システムを導入し、電子化を進めた場合の5つのメリットをご紹介します。
タイムカードに打刻された時間をExcelなどに転記して労働時間を集計する手間が削減できます。勤怠管理システムは自動計算が基本なので、手間と時間を短縮できるだけでなく、ミスの発生を抑える効果も期待できます。また、月半ばに労働時間を集計・把握することで、残業時間の超過防止の声掛けも可能になります。
労働基準法の第109条で、労働管理に関する重要書類は3年間の保管義務が定められています。タイムカードはこの書類に該当しているため、3年間の保管が必要でした。しかし、デジタル化すること紙での保存・管理の必要がなくなり、保管スペースにかかるコストが不要に。また、必要な書類の検索も簡便になります。
出勤・退勤を間違えて打刻してしまった際、タイムカードだとすぐに修正できません。個別の対応が必要なため、人事担当者の手間がかかっていました。しかし、勤怠管理システムで電子化してしまえば、何か操作や設定を間違えてもタイムカードより簡単に修正対応ができます。
残業時間を即時確認して管理を徹底できるので、従業員の労働時間の超過防止につながります。上司が部下の労働時間を簡単に確認できるようになるため、チーム内の負荷のばらつきにも気づきやすくなり、仕事の割り振りを検討する機会も得られるでしょう。するとチーム内に公平感が生まれ、モチベーションアップへとつながります。
タイムカードでの勤怠管理だと、働く場所が物理的に固定されてしまいます。つまり、出社が原則になってしまうので、柔軟な働き方の阻害要因になってしまうのです。タイムカードを打刻するために出社しなければいけない、という制限をなくすことで、柔軟な働き方へとスムーズにシフトできるようになります。
タイムカードの廃止・電子化にあたって、知っておきたいデメリットを2つご紹介します。
ほかのシステムを導入するときと同様に、「自社に最適なサービスの選定」「経営陣の説得」「全従業員への周知・操作説明」といった労力がかかります。ベンダーのサポートも得られますが、任せっきりにすることはできません。
たとえば、勤怠管理システムは全従業員が利用するものなので、全社的な周知・操作説明が欠かせません。マニュアルを配布するだけでなく、説明会を複数開催したり、操作方法がわからない人を個別フォローしたりと、丁寧な対応が必要になります。
ただし、これらの課題を乗り越えれば安定した運用ができるようになるので、結果的にはメリットがデメリットを上回ると考えられます。
自社の職場環境に合わない勤怠管理システムを導入してしまうと、タイムカードよりも出退勤記録の効率が落ちることがあります。
たとえば、指紋認証がスムーズにいかず何度か指をかざさなければいけない、ネット環境にトラブルが起きて出退勤の打刻ができない、スマホを忘れて出勤打刻ができない、といった不具合・トラブルが考えられます。また、出勤時間に1台のPCに人が集中して、打刻までに時間がかかってしまうこともあるでしょう。
そのため勤怠管理システムを選ぶ際には、「認証方法が職場環境に適しているか」「操作性に優れているか」「不具合は起きにくいか」といった点をチェックしておく必要があります。
出退勤を打刻する機能を搭載した勤怠管理システムを導入することで、タイムカードの電子化を実現できます。
人数や一部機能の制限、広告表示などがあるものの「タイムカード打刻」「出退勤データ集計」などの機能を搭載した無料システムをご紹介しています。コストを抑えて、タイムカードを電子化したい場合におすすめです。
無料の勤怠管理システム15選|ずっと無料or2カ月無料など
スマホやタブレット端末にアプリをインストールすれば、どこにいても迅速に出勤打刻ができるようになる勤怠管理アプリ。客先や現場への直行直帰やテレワークが多い組織には、アプリを使ったタイムカードの電子化がおすすめです。
勤怠管理アプリおすすめ15選!スマホで簡単に出退勤管理を
実際にタイムカードを廃止して、勤怠管理システムを導入した場合、費用はどのくらい変わるのでしょうか。結論、勤怠管理システムを導入するとタイムカードよりも月額費用が高くなる可能性が高いです。
ただし、システム導入によって、「人事担当者の業務負担が減る」「ペーパーレス化が進む」「多様さ働き方が実現できる」といったメリットを加味して検討することをおすすめします。具体的な費用感について、どちらもデバイスを購入する費用を含めた初期費用+月額費用でご紹介します。
タイムカードの打刻に必要なタイムレコーダーは一番シンプルなもので10,000円を切るくらいの価格です。「対応人数」「2色印字」「表裏間違えない機能」など細かな機能の違いはあるものの、10,000~30,000円で購入できるでしょう。
一方、集計データのUSBメモリへの書き出し、USBケーブルを使ったPCへのデータ書き出しなどに対応した高機能のタイムレコーダーは30,000~100,000円を超えるものまであります。
タイムレコーダーは買い切りが一般的なので月額費用は掛かりませんが、消耗品代がかかります。タイムカードは大容量パックで購入すれば、安いもので1枚約20~30円、インクは1,000円未満~数千円まで。どちらも利用人数によって消耗の期間が変わります。
クラウド型の勤怠管理システムの場合の試算です。共有PCや各自のPC・スマホで行うタイプの場合、初期費用はかかりません。月額費用は1人当たり200~300円程度が主流です。
PCにケーブルでつないで利用するタイプのICカードリーダーは数千円で購入できます。デジタル版のタイムレコーダーとして使える、ICカードリーダーや指紋認証機器だと20,000~100,000円程度です。
なお、各自のSuicaやICチップ付きの社員証が対応していれば、それのICカードをそのまま勤怠管理用に利用することもできます。もし対応していない場合は別途ICカードの用意が必要です。社員数が多い場合は、ICカードを新規導入するより、指紋認証等のデバイスを導入する方が安価になります。
最後にご紹介したいのが、勤怠管理システムを導入する場合に、タイムカード管理からシステムに切り替える際の注意点です。大きく3つご紹介します。
「PCが1人1台支給されているのか、複数人で1台を利用するのか」といった設備や、「全員が決まった時間に一斉に出社するのか、シフト制でバラバラなのか」といった出退勤時のピーク人数など、職場環境に応じて最適なツールが異なります。
たとえば、商品の在庫確認など勤怠管理以外にも利用する必要があると、PC利用が混み合ってしまい不便でしょう。店舗にPCが1台しかない場合は、スマホやICカードリーダーのような別デバイスの設置・利用がおすすめです。
また、同じ時間帯に大勢の社員が出社する場合、指紋や顔認証だと一人ひとりの打刻に時間がかかりがちです。スマホやPCから各人が打刻できるシステムを選んだり、初期費用の安い共有デバイスを複数購入したりして、打刻場所を社内各所に分散させる工夫があるとよいでしょう。
勤怠管理システムを導入する場合は、機能のカバー範囲の確認も必要です。
勤怠管理システムには、「勤怠が登録できればいい」というシンプルなニーズを叶えるものから、「休暇申請などのワークフローも組み込みたい」「給与計算ソフトと連携して毎月の集計作業を効率化したい」といった導入後のニーズに対応するものまで様々。どこまでの範囲で利用したいのかを視野にいれて検討しましょう。
特に、広範囲をカバーしたい場合は、「ワークフローを自社仕様にカスタマイズできるか」「利用中のソフトと連携可能か」などのポイントも要チェックです。
打刻や申請方法を変えることで、新しい業務フローを覚えたり、勤怠管理システムの操作方法を覚えたりといった手間が発生します。これまでのやり方に慣れていた従業員からすると、不便に感じることもあるでしょう。
しかし、勤怠管理システムが浸透することで、経営層・マネジメント層・現場のメンバーのいずれにとっても非常に大きなメリットがあるのは確かです。時間は少しかかるかもしれませんが、全従業員に導入メリットの理解を求めることが大切です。
ここまでタイムレコーダーの廃止、勤怠管理システムを導入しての電子化について、ご紹介してきました。タイムカードを電子化して勤怠管理システムに移行すると「集計作業の効率化」「労働時間の管理の強化」「紙保管の抑制」「労働時間を正確に把握できる」「柔軟な働き方を可能にする」などのメリットが得られるでしょう。
そして、勤怠管理システムはただの社内の管理システムではなく、うまく使えば社員のモチベーションアップ、内部統制の強化、営業力の向上にもつながります。アナログなタイムレコーダーから、デジタルの勤怠管理システムを導入する際には、管理の対象になる人員の数やコストを踏まえて検討することをおすすめします。
勤怠管理システムの選び方はこちらで解説しています。
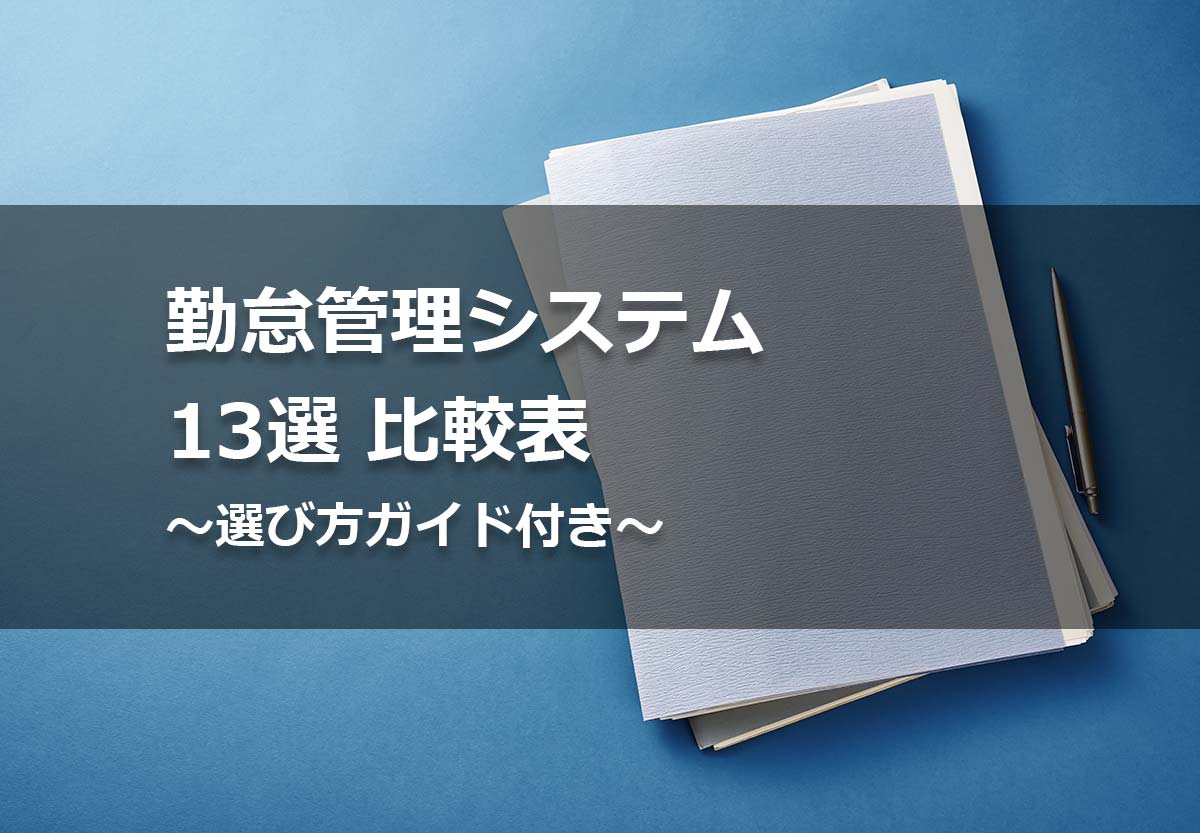
勤怠管理システムの比較表
勤怠管理システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“勤怠管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
アマノビジネスソリューションズ株式会社
アマノグループが提供する勤怠管理クラウドサービス。初期費用・基本料金なし、月次費用は完全従量課金なので、少人数や繁閑の人数変動があっても無駄なコストをかけずに導...
株式会社マネーフォワード
打刻・集計などの勤怠管理をラクに効率化。働き方改革関連法への対応、シンプルで使いやすい操作画面、給与計算ソフトとの連携も強み。...
株式会社スマレジ
小売・飲食・サービス業を中心に豊富な導入実績を持つクラウド勤怠管理システム。勤怠データを利用して自動で給与計算や年末調整もできます。30名までなら無料で勤怠管理...
株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー
エンタープライズの多様な働き方に対応するSaaS 型勤務管理システムです。休暇管理や工数管理など豊富な機能を搭載し、働きやすい環境づくりに適した充実の機能を提供...
キンタイミライ(旧:バイバイ タイムカード)|インタビュー掲載
株式会社ネオレックス
3,000人以上規模で11年連続シェアNo.1、利用者数33万以上の実績を保有。店舗や作業現場等がある業界・業種に特に強い。...
株式会社ヒューマンテクノロジーズ
導入企業67,000社以上。充実の人事給与機能も備えた、市場シェアNO.1のクラウド勤怠システム。規模・業種に関係なく、オフィス、店舗、在宅勤務、外出先など、あ...
中央システム株式会社
月額1人100円で打刻・勤務集計・データ出力・有休/休暇管理・申請/承認・36協定管理等、追加料金なしですべての機能が使える機能と価格のバランスが優れた勤怠管理...
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。
資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。
なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。