広報・マーケ・リスク管理で膨大な情報の検索・照合作業に追われる担当者へ。AIファクトチェックの仕組みと限界、選定ポイント、おすすめツールを紹介します。
AIファクトチェックとは、生成AIツールと検索エンジン技術を組み合わせることで、「テキストや画像・動画が、事実に基づくかどうか」を効率的・効果的に検証することのできるサービスです。
たとえば、Web記事やプレスリリース、SNSの投稿文などを入力するだけで、すばやく解析し、根拠となる外部情報の有無や矛盾点を提示してくれます。事の成否だけでなく、一次情報へのリンクを表示してくれるため、出典の実在を目視で照合可能。従来の手作業による確認作業を大幅に短縮できるのがポイントです。
近年では、複数のデータベースを横断した証拠の時系列表示や、生成AI特有の文章パターンやフェイク画像・動画の検知もできるサービスも増加。多くが月額課金のサブスク制のため、大企業だけではなく、中小企業・個人事業者でもAIを駆使した高精度なファクトチェックを利用できる点が魅力です。
近年、個人・企業を問わず、販促・マーケティングやPRなど、様々な理由により、情報発信する機会が増えています。指示するだけで文面や画像を大量に生成してくれる生成AIの普及もそれに拍車をかけています。利便性向上の観点からも、こういった流れは今後更に加速していくと考えられます。
しかし、その一方、コンプライアンス強化が進んだ今の世の中では、SNSでは一度誤情報が拡散してしまうと、株価下落や取引停止にまでつながるおそれもあります。生成AIも単に便利なだけではなく、部分的に誤情報を含む「半真実」を出力するなど、利用にリスクが伴うのを忘れてはいけません。
これらを防止するためには、発信する情報が「事実に基づくものか」ファクトチェックが重要ですが、爆発的に増加する情報量に対して、人力によるファクトチェックだけでは対応に限界があります。そんな中、注目を集めているのが、自動でファクトチェックができるAIファクトチェックツールです。
AIファクトチェックツールは「抽出→検索→照合」という流れで事実を確認しています。
①抽出:文章から「主張・数値・固有名詞」を抜き出す
②検索:Webやデータベースで根拠を検索する
③照合:見つけた証拠と照らし合わせて結論と出典のリンクを返す
気になるのは、「検索」や「照合」の工程で得られる精度でしょう。
とある研究論文のベンチマークでは、AIがネット上で公開されているページ(公式サイト、報道、ブログなど)だけを「検索」して、原稿の主張と機械的に「照合」する方法において、人力で一連の工程を行った場合との一致率がおおむね7割前後という報告があります。これは「短時間で大枠を把握する」用途なら十分、実用水準といえます。
ただし、最新ニュースのような直近情報が関連してくると、AIファクトチェックツールの精度は下がります。また、ツールによってはそれ以外にも様々な弱点が。個々のリスク・対処方法の詳細については「AIファクトチェックのリスクと対応策」で後述しています。先に知りたい方はそちらをご覧ください。
AIファクトチェックツールは様々な部署・業務にメリットをもたらしますが、ニーズは部署ごとに異なります。共通したメリットとしては「人員が限られていても膨大な情報の確認負担軽減」が挙げられますが、それ以外の部分について個別のケースごとに細かく確認していきましょう。
メディア向け発表資料やSNS投稿などについては、発信前に「誤記・誇張がないか」校閲は必須です。ただし、より正確を期すには膨大な情報と照合しなければならない場合もあり、校閲作業に丸一日かかってしまうことも珍しくはありません。
AIファクトチェックツールなら、AIが学習した情報と照合して誤記をハイライトし、過去リリースとの整合性も自動比較。校閲作業を数分に短縮して、自社の発信情報の信頼性を高められます。
正しく市場調査や競合分析を行う上では、公開情報から正確に情報を抽出し、検索・整理することが問われます。しかし、該当情報が本当に正確か、古くなっていないか、過度なポジショントークが混じっていないかなどを確認するには様々な情報源から多角的にチェックすることが必要です。これら作業をすべて人力で行うのは大きな負担です。
AIファクトチェックツールなら、根拠リンク付きで公開情報の真偽をチェックするため、検索・整理の作業を迅速化。調査・分析のスピードが上がり、自社の戦略ミス防止につながります。
上場企業などでは、企業経営の様々な局面でファクトチェックが求められます。しかし、SNS、IR資料や契約書、社内通達や通報窓口メールなど、情報が膨大な量に及ぶため、すべてを人手で点検・監視することは容易ではありません。業務効率はもとより、重大リスクの見落としや初動遅れも課題です。
AIファクトチェックツールなら、社内外文書はもちろん、SNSも監視可能。中には24時間モニタリングすることで、文書中の虚偽記載や機密漏えいの兆候を見つけることができるものも。
SNS監視について詳細を知りたい方は「SNS投稿監視サービスの比較11選」をご覧ください。専用サービスを紹介しています。
従来は、原稿を読んでいて「おや?」と違和感を覚える箇所があれば、都度検索し、表記ゆれや古い統計データ・数字を人力で修正していました。しかし、より精度を高める上では、あわせて論文や政府統計など信頼性ある出典元を検索するなど、膨大な情報量を比較・精査する必要があります。
AIファクトチェックツールなら、原稿内の固有名詞・統計データを自動抽出し、政府統計・論文・公式サイトの候補URLを提示してくれます。提示されたリンク先を確認すれば、一次情報の裏取りが完結するので、トータルの校閲時間を大幅短縮しつつ原稿の品質を安定させられます。
複数のレポートから、市場規模や競合動向を手作業で突き合わせ、統計やトレンドの信頼度を吟味しながら古いデータや過大推計が混入していないかを確認するなど、人力で行うのは大きな負担です。また、レポートに誤りや不十分な見通しがあるのに見落としてしまえば、事業計画の成否に直結するリスクにもなります。
AIファクトチェックツールなら、新規事業に関する仮説やKPIを入力すれば、最新ニュース・調査との一致・矛盾を色分けして、出典も提示しつつ、見やすいレポートに書き出してくれます。意思決定に至るまでの検討スピードと精度を高められます。
AIファクトチェックツールは様々な作業負担を大幅に軽減できますが、万能ではありません。以下のようなAIの弱点を理解した上で、対応策を組み合わせることが欠かせません。判定・回答はあくまで参考意見に留め、最終的な選択・決定の前には必ず人力での再チェックもした上で、責任を持って判断しましょう。
現在普及するAIを支える大規模言語モデル(LLM)は、わからないことをわからないとは率直に回答せず、"知ったかぶり"をする傾向にあります。
たとえば、存在しない市場データを創作して、それを引用したプレス発表が実在するかのように出力することがあります。「Perplexity」や「Genspark」のように根拠となる出典URLを自動添付するツールを使い、リンク先の実在と内容を必ず確認できるようにすれば、ハルシネーションのリスクを低減できます。
LLMは仕組み上、既存の学習データをもとに回答します。そのため、学習時点によっては、法改正や新製品の知識を更新できておらず、誤った出力してしまう恐れがあります。対策としては、その都度、ネットで最新情報を探して照合できる仕組みを使うと有用です。
たとえば、AIツールを利用する際には、「学習データに頼らずに、必ずリアルタイムで検索する」「直近3カ月、新しい公式発表や省庁資料がないか人力で再チェックする」などの手順を業務フローに組み込んで標準化しておくと、ツールの知識更新遅れによる見落としを防止できて安全です。
そのほか、「Gemini」のようにWebブラウジング機能に強みを持ったものを利用すれば、回答中にGoogle検索で見つけた一次情報を並べ、合っている点・矛盾する点があればハイライトすることも可能です。
AIによっては、比喩や皮肉を人間のようには受け取らず、文字通りに受け取ってしまうおそれがあります。
たとえば、高性能への称賛を込めて「この製品は化け物だ!」と比喩すると"危険な製品"と解釈したり、不具合への不満を「最高のアップデートだね」と皮肉ると"高評価"と誤読したりします。その他、文章が長大で複雑だと、AIが答えてほしい要点以外に着目して回答を済ましてしまう場合もあります。
対策はAIへの質問を1点に絞ることと、文を小分けにして与えること。例としては以下の方法があり、AIの文脈誤読や要領を得ない回答を大幅に減らせます。
AIは「学ぶ材料(集めた記事・統計・動画など)」が偏ると、答えも偏ります。たとえば、英語圏ニュースばかりを学習していると、日本独自の事情・背景を誤解しがちです。AIを使用して情報収集が捗っても、収集できた情報に偏りがあると、結局人力で精読する必要が出てしまうため意味がありません。
対策としては、「NotebookLM」のように、複数リソースの情報を一括投入できるAIファクトチェックツールを利用すること。たとえば、「省庁白書+業界レポート+反対意見のブログ記事」を読み込ませて、「主張ごとの賛否と根拠を一覧化して」と指示することでそれぞれの傾向を把握できます。ほかにも、「Perplexity」で出典リンク必須の別ツールを用いてクロスチェックすると、偏りを可視化して、判断のブレを減らせます。
自社に合ったAIファクトチェックツールを選ぶ上では、「何を確認したいか」が重要です。それによって選ぶべきツールは大きく3タイプに分かれます。以下、それぞれのタイプについて説明します。目的と業務フローを照らし合わせ、最適な機能を持つサービスを導入しましょう。
自社記事や広告、プレスリリースなど「公開前の情報について誤記や過大表現を出稿前に洗い出したい」という広報・PR担当者、マーケティング担当者、編集・コンテンツ制作部門向けのタイプです。
たとえば、「NotebookLM」や「ChatGPT Pro」「Genspark」では、元の原稿をアップロードすると、文章中の固有名詞・統計データ・数値を抽出し、一次情報がないか検索。照合して疑義があれば該当箇所を明示してくれます。
回答結果を社内でダブルチェックする仕組みにすれば、確認・校閲にかかる負担を軽減して発信情報の品質を底上げできます。
速報ベースで流れる「噂や競合情報の正確性を即座に判定したい」というリスク・コンプライアンス部門、SNS担当者、経営企画向けのタイプです。拡散スピードが早い話題でも「信頼できる情報か?」の裏取りをすぐに検証できます。
たとえば、「Gemini」「Grok」は情報をリアルタイムで検索して情報の根拠URLを時系列に沿って提示します。特に「Grok」は、SNSのX上の投稿をリアルタイム検索できるので、従来は噂レベルの話題のため検証を見送っていた情報でも検証できます。
最近では、SNS上の詐欺広告に著名人が無断に使用される事例が記憶に新しいです。こういった「ディープフェイクによる著名人の偽動画や偽造製品画像を検知したい」という広報・PR担当者、リスク・コンプライアンス部門向けには、画像・動画が本物かを瞬時に識別してくれるこちらのタイプがおすすめです。
たとえば、「SYNTHETIQ VISION」や「Deepware Scanner」は数十秒で「合成の疑い」を点数や色で表示し、怪しい部分を囲って示します。フェイク動画を見分ける「HIVE MODERATION」は動画フレーム単位の顔特徴点を照合してスコア化して検知します。
AIファクトチェックツールの特徴や注意点、部署別の選び方を把握できたら、次は使用する際の比較ポイントを確認しましょう。
ファクトチェックでは、結論だけでなく「なぜそう判断したか」を第三者が元情報を辿って確認できる必要があります。ツールによっては、回答文中にURL付き引用をインライン表示(文中に都度表示)するものもあれば、最後に参考一覧をまとめて示すものもあります。
たとえば、「Perplexity」は段落ごとに出典を脚注表示。「Gemini」は回答に関連するリンクを文中脚注ではなくパネルやリンクチップなど別枠で表示します。業務でAIを利用する場合は、「どの形式が出典元を確認しやすく、レビューしやすいか」を軸に検討すると良いでしょう。
製品・サービス開発においては、最新情報を他社よりもいかに早く正確に取得できるかが、成功のカギとなります。ほかにも製品リコールやソフトウェア脆弱性の即時確認などもリアルタイム性が求められる場面にも当てはまります。この場合は、ツールが検索エンジンと連携してリアルタイムで情報を取得できると便利です。
たとえば、「Grok」は投稿直後のXスレッドを即時取得でき、「Gemini」はGoogle検索をバックエンドに自動再クエリして最新記事を埋め込みます。
AIファクトチェックツールによって、対応するメディアは異なります。そのため、チェックしたい対象がテキスト中心なのか、それとも画像・動画・音声が混在するのかでツールの選択肢も変わります。
たとえば、「Gemini」「ChatGPT(Pro)」は画像・動画・音声と多様なデータにも対応したマルチモーダルなツール。文章の解析に強くテキスト中心の利用ならおすすめの選択肢です。
一方、画像や動画のディープフェイク対策まで必要なら、「SYNTHETIQ VISION」「Deepware Scanner」「HIVE MODERATION」と画像・動画に特化したツールを選ぶのがおすすめです。

(出所:NotebookLM公式Webサイト)
Googleが運営するアップロードした資料を整理・要約できるAIツール。PDF・スプレッドシート・社内wikiなど多様な形式もまるごと取り込み、要約・引用・脚注付き回答を生成。たとえば、決算資料をアップすると、売上高の変遷を根拠リンク付きで抽出してくれる。アップロードできる資料が自社に大量にある場合の情報整理におすすめ。Googleアカウントさえあれば一定条件のもと無料で利用可能。Google WorkspaceやGoogle cloudの契約者は有料プランを無料で利用可能。
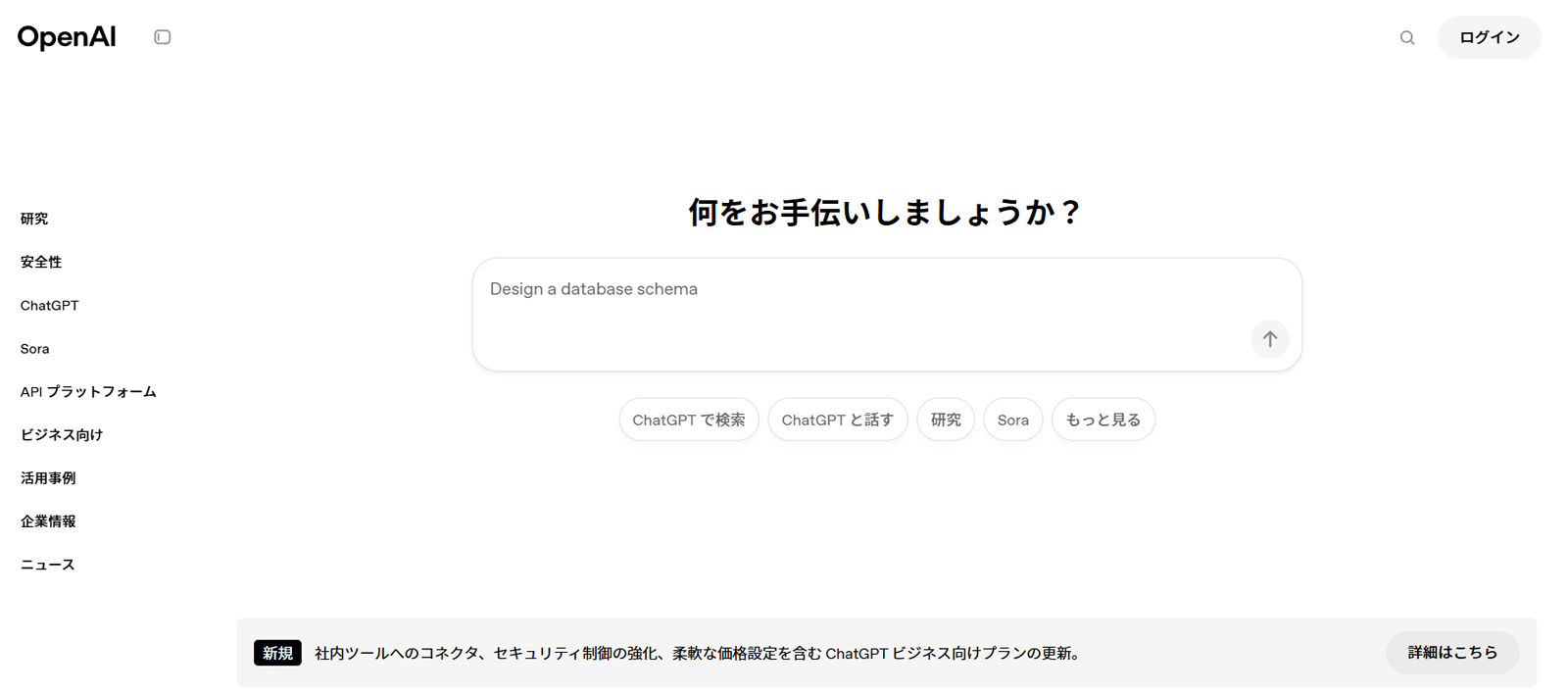
(出所:ChatGPT公式Webサイト)
現在の生成AIブームの火付け役であるChatGPT。世界最高品質の大規模言語モデルを背景にしたマルチモーダル対応。精度の高いテキスト校閲を望むのであれば最も高性能なProプランがおすすめ。ブラウジング機能をオンにすれば外部データソースも併用でき、ファクトチェック補助と文章品質向上を一度にこなせる点が魅力。

(出所:Genspark公式Webサイト)
複数のAIエージェントが同一ドキュメントを別視点で検証し、結果を突き合わせるクロスチェック型のAIファクトチェックツール。誤記が疑われる箇所はスクリーンショットと出典URLを並べて提示するため、見やすいレイアウトで社内の情報共有や検証を効率化。第三者視点で客観性を担保したいプレスリリースや調査レポートに最適。
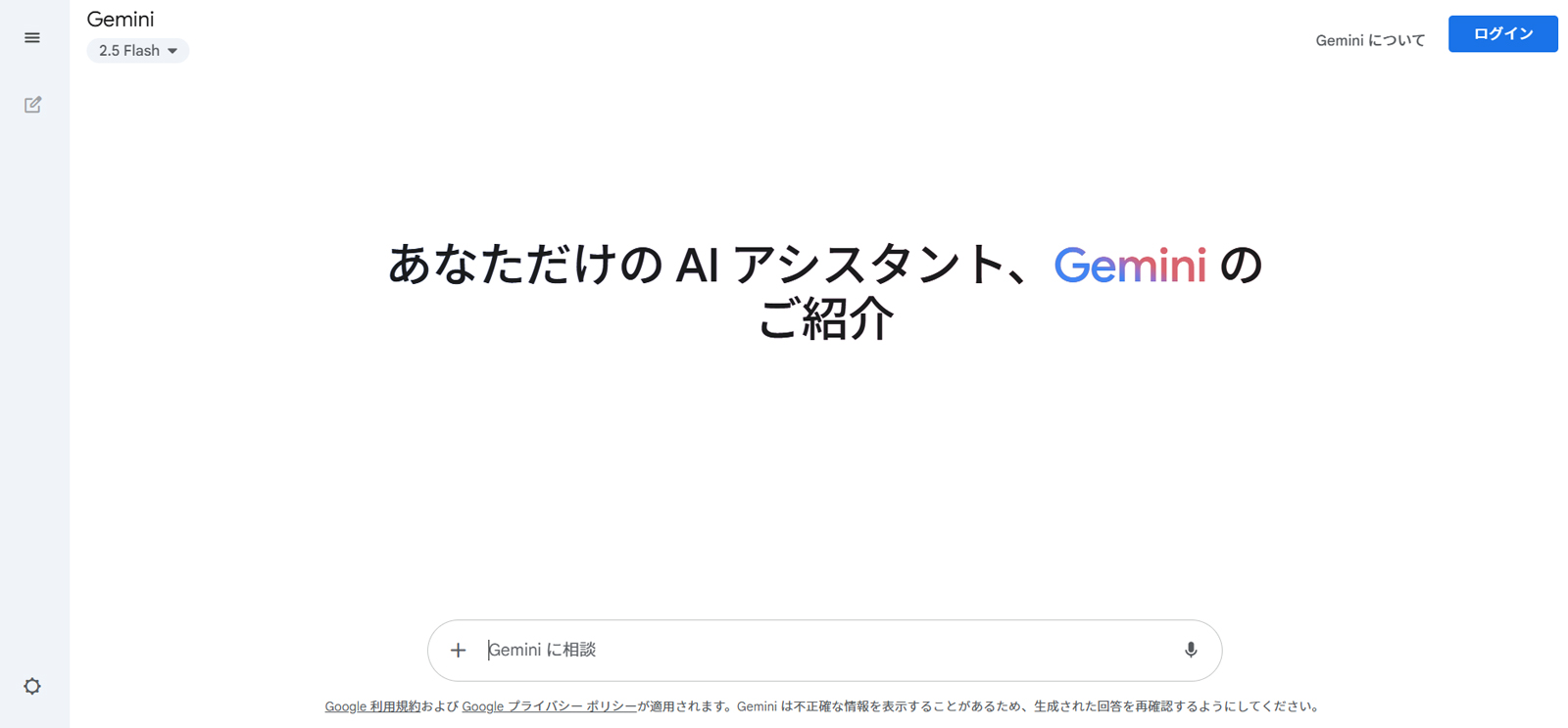
(出所:Gemini公式Webサイト)
Google検索とシームレスに連携し、回答内で一致・矛盾箇所を自動ハイライト。たとえば、「競合が新製品を発表した」というX上の投稿をコピペで入力するだけで、公式サイトなど主要サイトを検索・照合し迅速な事実確認が行える。Google検索と連携しているため、最新情報の検索にも強い。
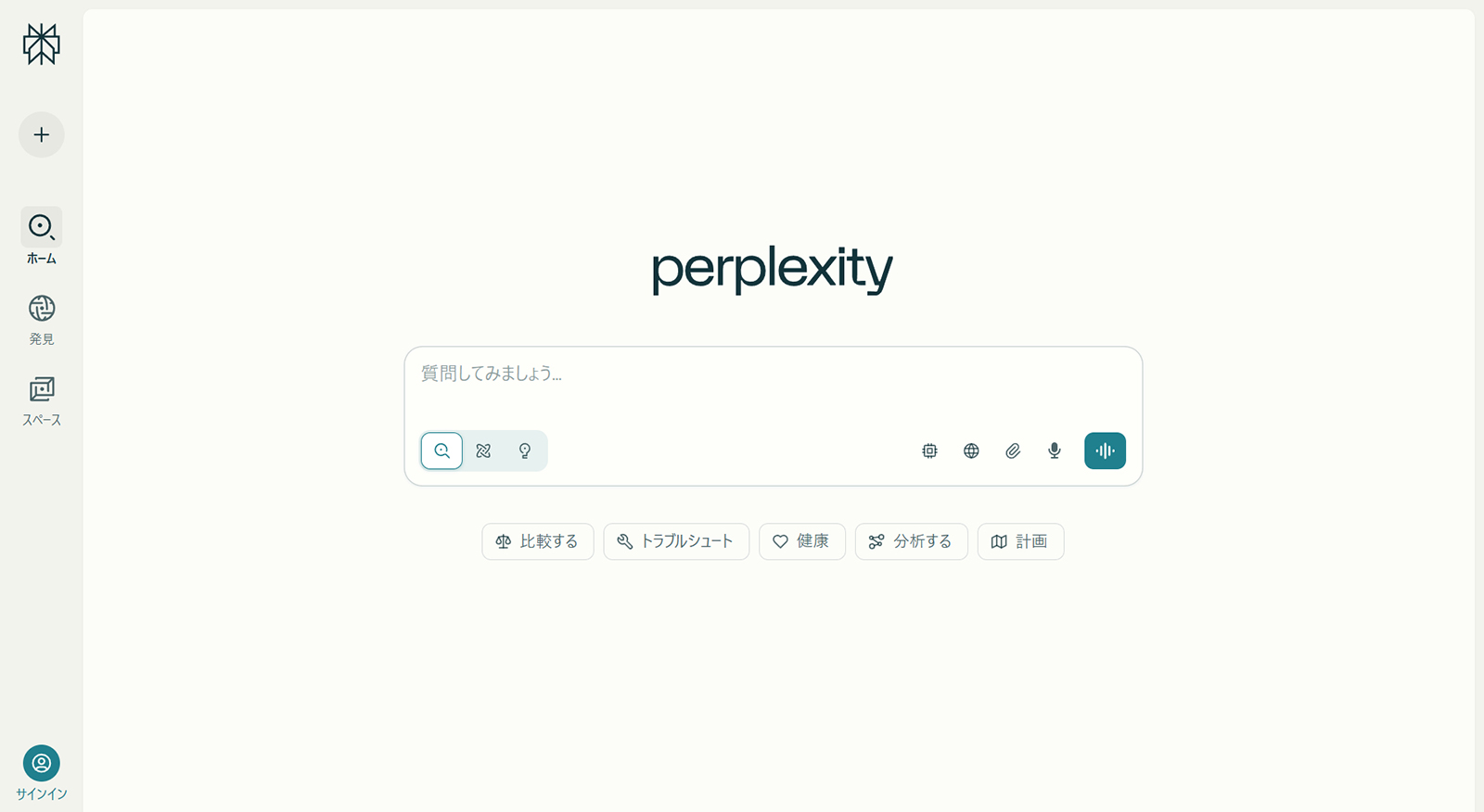
(出所:Perplexity公式Webサイト)
回答に必ず出典リンクを付ける仕様が特長で、「AI検索エンジン」のパイオニア的ツール。回答と同時に「ソース」「ステップ」を横並びで提示し、検索の経過を追いかけてくれる見やすいUIも特徴。回答の末には「関連」という欄でほかの質問案も提示してくれるため、より深掘りした質問と回答ができる。
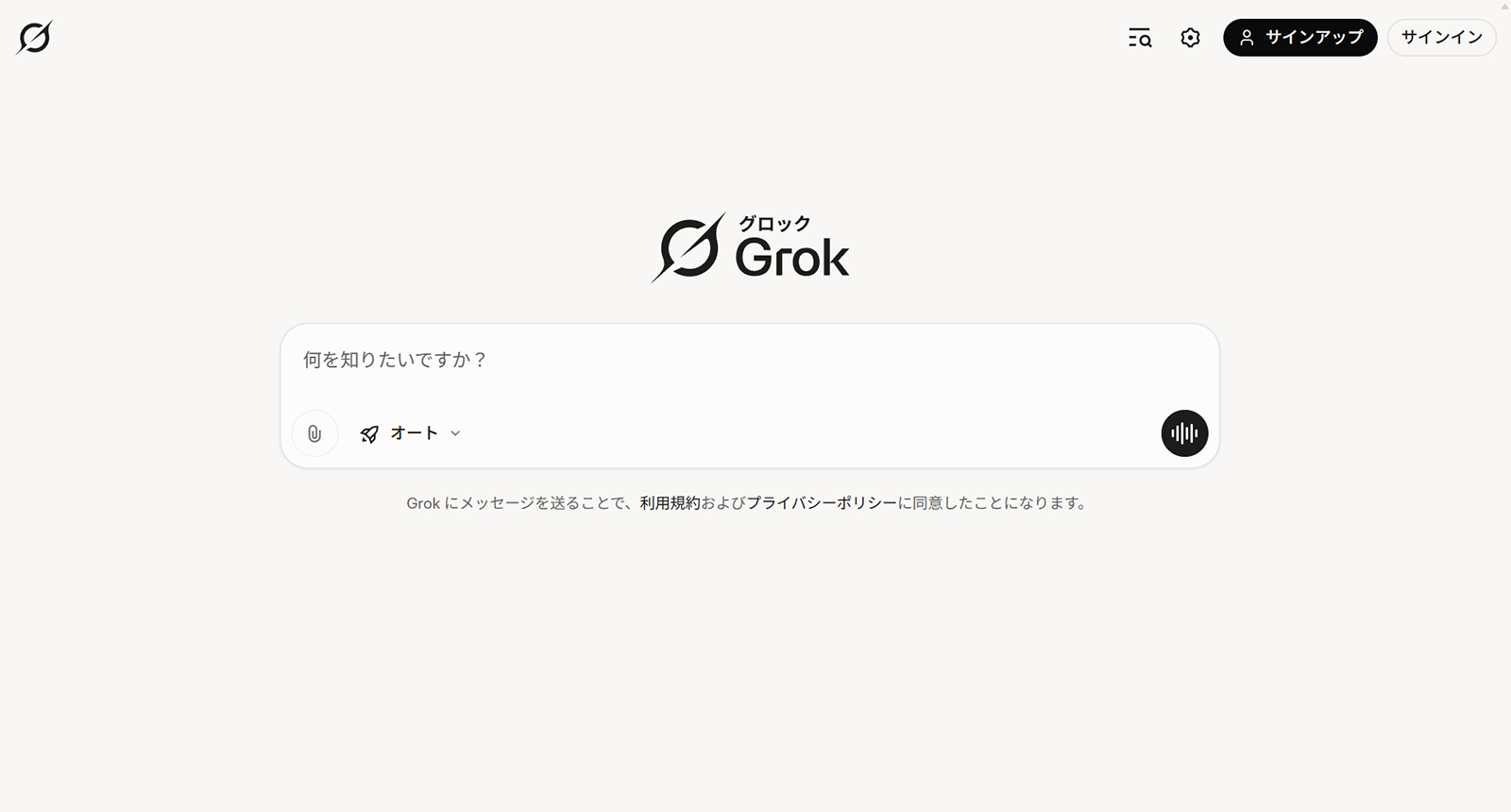
(出所:Grok公式Webサイト)
X(旧Twitter)と連携し、投稿を入力すると外部リンク・過去発言・メディア(画像など)を総合評価。拡散速度が速いトピックでも、「根拠の弱い推測」「既に否定された情報」などを検証し、炎上対策に取り組むSNS担当者向け。XのUIに統合された「X版Grok」とブラウザで独自に利用する「アプリ版Grok」があり、SNSであるXとは切り離してAIチャットに集中したい場合はアプリ版Grokがおすすめ。
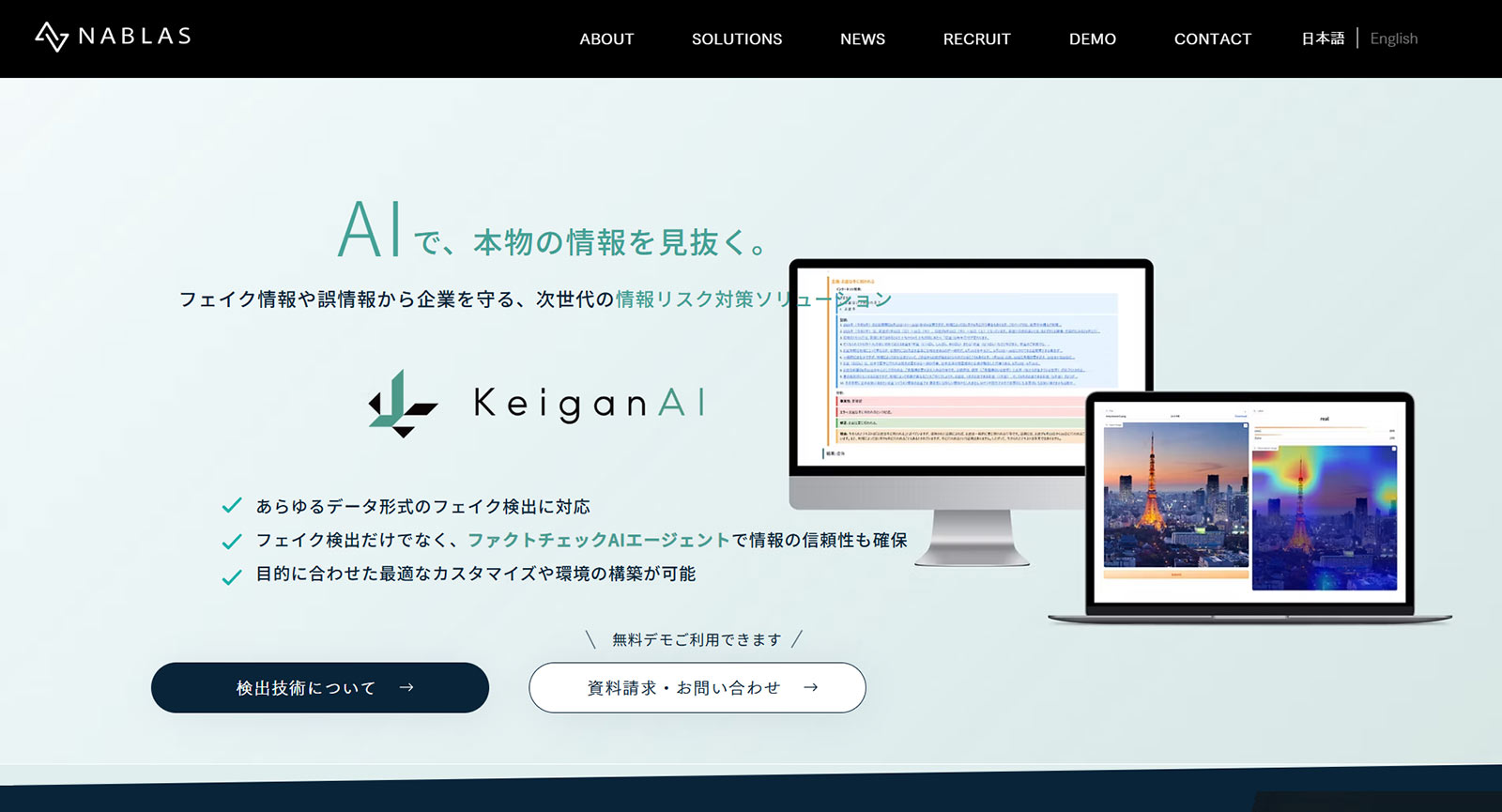
(出所:keiganAI公式Webサイト)
東大発のスタートアップ企業Nablasが提供する企業向け画像・動画解析AI。JPEG/PNG/MP4などをアップロードすると、改ざん痕をヒートマップで可視化し「生成AI由来」「部分修正あり」などを自動判定。官公庁や国内報道機関の試験導入例もあり、災害報道やIR資料の真正性確認に活用されている。
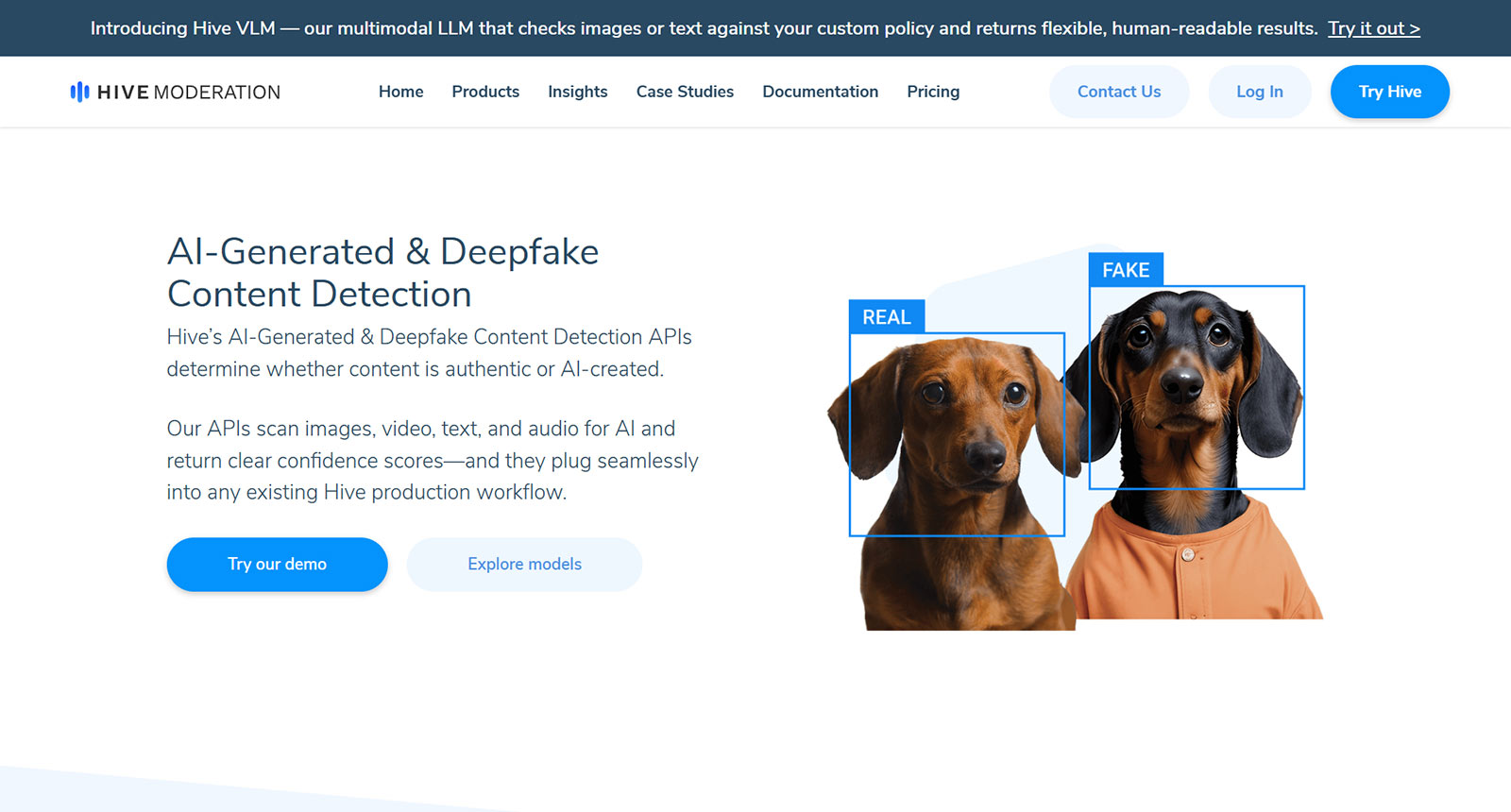
(出所:HIVE MODERATION公式Webサイト)
ハリウッド大手スタジオが採用するコンテンツ安全性検出AI。画像・動画・音声を一括スキャンし、「ai_generated」「not_ai_generated」でスコアリング。高精度の検出により、音声なりすましによる詐欺電話対策、フェイクニュース対策、知的財産保護への利用実績がある。児童性的搾取撲滅に取り組むことも表明。
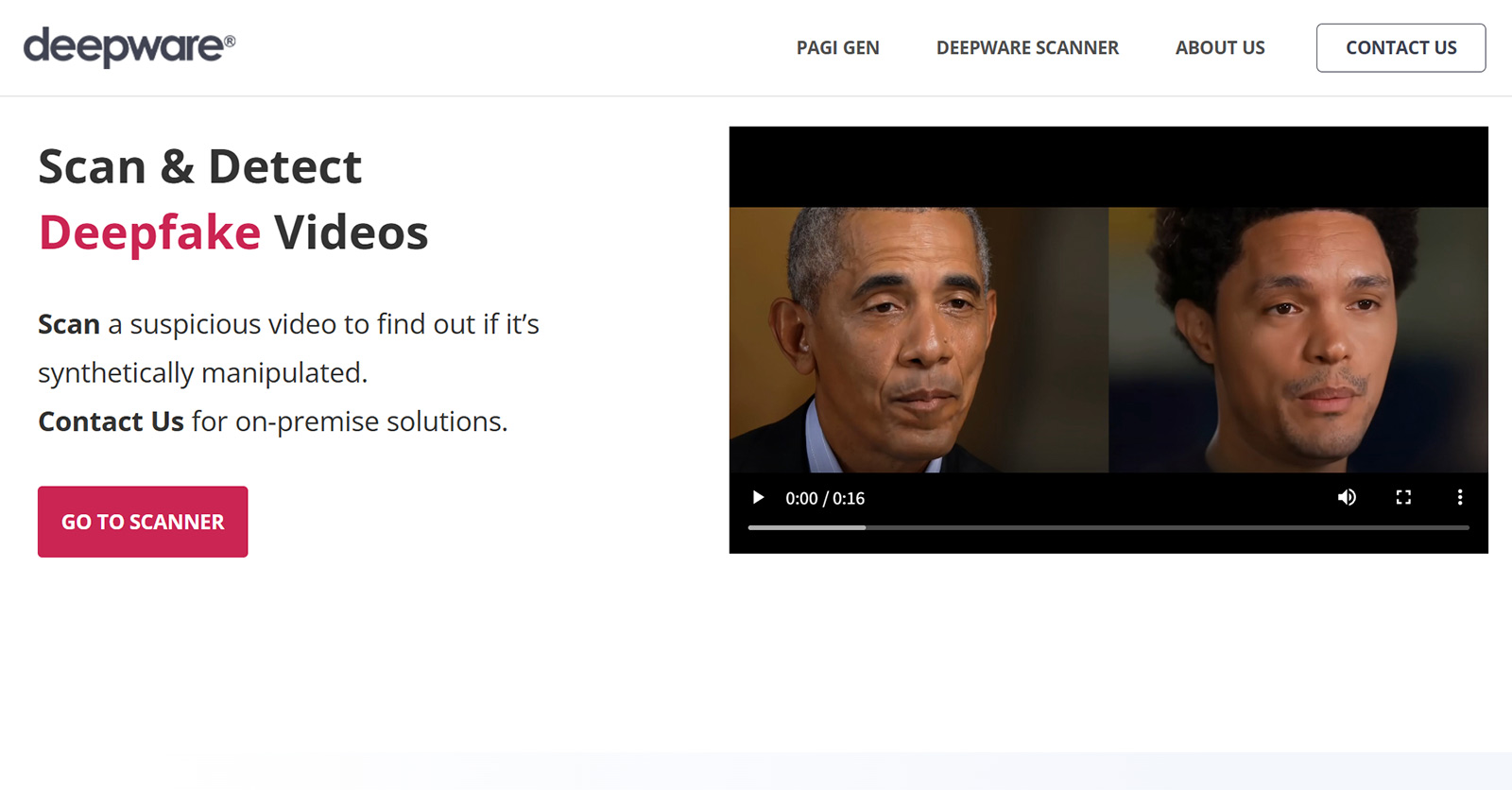
(出所:Deepware Scanner公式Webサイト)
ブラウザで利用できるディープフェイク動画の検出ツール。フレーム間の顔特徴点・口元と音声の同期ズレ・圧縮ノイズを多角的に分析し、信頼度スコアを提示。著名人を狙った偽インタビュー動画や合成スピーチの早期発見に強い。YouTubeなど動画サイトのURLを入力して手軽にフェイクかどうか検証可能。

(出所:SYNTHETIQ VISION公式Webサイト)
国立情報学研究所の研究成果をベースにしたディープフェイク検出API。高解像度フレーム比較と独自の顔認証アルゴリズムで、AI生成画像やフェイク動画を高精度に判定。複数の国内企業に有償ライセンスを実施している。
AIファクトチェックツールはテキスト、SNS上の投稿、画像・動画など、様々なデータの正確性を短時間でチェックできる有益なツールです。
AIファクトチェックツールは、目的と業務フローを応じて、以下のタイプに分けられます。
①発信情報の正確性を確認したい
②外部情報(SNS・ニュース)の真偽を見抜きたい
③画像・動画がAI生成されたものか判定したい
それぞれのタイプに合った特性をふまえつつ、業務別の利用シーンに最適なツールを見極めることが重要です。ただし、AIには課題も多いことから、現状では「万能ではない」という点を理解した上で、人力でのチェックとの併用で利用することをおすすめします。
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。
資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。
なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。