社内に分散したノウハウを1カ所にまとめたり、ナレッジを蓄積したりするために社内wikiツールの導入を検討している方へ。社内wikiツールの導入メリットや社内浸透策とともに、オープンソースの無料で使えるツールもあわせて、おすすめのツールを紹介します。
“社内wikiツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)
社内wikiツールとは、社内の情報やノウハウを蓄積・共有するためのwiki型ツールです。対象となる情報としては、業務に関するノウハウやマニュアル、FAQ、議事録など、更新性の高いものが挙げられます。社員なら誰でも自由に、ドキュメントや記事ページを作成・編集することができるのが特徴です。
社内wikiとは、「ウィキペディア(wikipedia)」にちなんで、WebブラウザからWebサイト上のページに追加・記載・更新などを直接行える、社内専用のWebサイト編集システムのことです。
通常、従業員が業務でよく利用するのはメールやチャットなどのコミュニケーションツールですが、「時間が経つと情報が流れてしまう」という課題があります。その点、社内wikiであれば、情報を逐次ストックが可能に。特定の管理者に依存せずに従業員全員が自由に編集できるため、必要に応じて新しい情報の追加・更新が行えるといったメンテナンス性の高さも大きなポイントです。
社内wikiツールを導入するときに注意したい、3つのポイントについて解説します。
「自由に書いてください」とアナウンスするだけでは足りません。書き込みを活性化させるためにはナレッジ共有の必要性を周知したり、アウトプットを促す仕組みを作ったりといった浸透施策が必要です。
情報は保管場所を分けるのではなく、なるべく1カ所にまとめて運用しましょう。「何がどこにあるのかわからない」という状態を避けるために、ディレクトリ整理やラベル付けによって情報の検索性を高めるといった取り組みが必要です。
チャットツール、社内掲示板、社内SNS、文書管理ツールなど、利用ツールが増えると混乱が生じるため、できるだけツールを絞るのがおすすめです。複数併用する場合は、それぞれの特徴を活かした運用ルールを定め、迷わず使いこなせるよう工夫する必要があります。
今回は、社内wikiを推進していくうえで、おすすめの社内wikiツールや具体的な導入メリット、社内浸透策などをあわせて紹介します。
社内wikiツールをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“社内wikiツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)
社内wikiツール導入によって得られる、5つのメリットを解説します。「どんな課題が解決できるか」もあわせて紹介しているため、自社で抱えている課題と照らし合わせながら確認しましょう。
社内wikiツールを導入すれば、事務処理に関するFAQをまとめておいたり、業務知識をナレッジ化したりすることで、些細な疑問のセルフ解決を促進。業務の効率化につなげられます。それ以外にも、会議前に過去のアジェンダを事前共有するといった使い方も可能に。認識合わせや前提知識の共有に時間をかけることなく、議論をスムーズに進められます。
社内の誰かが経験済みの業務や、解決済みのトラブルに関するノウハウが共有されていれば、同じ問題が発生した際、スムーズに解決策を実行できるように。加えて、共有されているノウハウを社員がそれぞれブラッシュアップすることで、業務品質の向上にもつながります。
業務内容やルールをまとめた社内wikiがあれば、新入社員や部署異動でやってきたメンバーへの研修を簡略化するのに役立ちます。研修担当者の負荷を減らすだけでなく、新メンバー自身も「ここを見れば大丈夫」と安心感を持って、新しい業務に取り組めるように。
社内wikiなら誰でもページを作成・更新できるため、社内全体で情報共有がされやすくなります。また、誰かが投稿したナレッジをほかの社員がブラッシュアップするといった、コラボレーション効果も期待できるでしょう。なお、ほとんどのツールが、情報によって閲覧・編集権限を狭めるといった措置も取れるため、採用情報・個人情報などを取り扱う場合も安心です。
ページ作成に特定知識の習得が必要だったり、フォーマットが複雑だったりすると、書くのが億劫になって更新が滞りがちに。その点、社内wikiツールの多くは、シンプルな記載方法や多様なフォーマットを採用しているため心配いりません。また、文字装飾やリスト形式での記載など、幅広いテキスト表現ができるMarkdownに対応しているツールもあります。
「せっかくツールを導入したのに今ひとつ使いこなせていない…」といった導入失敗を防ぐため、社内wikiツールを社内で浸透させるための4つの方法を紹介します。
「社内wikiツールを導入したら自然とみんなが使ってくれる」というケースは非常に稀です。導入目的や使い方をアナウンスしても、なかなか浸透が進まないことも。
そのため、導入に強く賛同する複数人でチームを作って長期的な社内啓蒙活動を行うのが、導入成功のポイントとなります。1人の担当者に任せてしまうと、作業量とメンタルの両面で負荷が大きすぎるため、「チームで対応する」ことが重要です。
また、チーム内で導入から浸透までのロードマップを作成すれば、着実な利用者の増加につなげられるでしょう。
社内wikiの活用が進まない理由に、「すぐやらなくても困らない」「アウトプットをしたところで見返りが少ない」といったものが挙げられます。そのため、積極的に書き込んでナレッジを共有してくれた人にインセンティブを支給する制度や、アウトプットに対する感謝や称賛を見える化する仕組みを作り、社内浸透を図るのも一手です。
運用を開始する際に社内wikiが白紙の状態だと、「何から書き始めたらよいかわからない」「コンテンツがないから閲覧しない」といった理由で過疎化しがちに。
前述の導入推進チームにて見本となるコンテンツを事前に投入しておけば、書き方のコツが伝わるのに加え、閲覧者の増加も期待できます。業務に関わるナレッジから、社員のプライベートの様子やおすすめのランチ場所まで、様々な内容のコンテンツを用意しておくと、社内wikiを見たくなったり、書き込みたくなったりする社員も増えるはずです。
社内wikiを運用するにあたって一定のルールは必要ですが、ルールが細かすぎるとどうしても書きづらくなってしまうように。運用が上手くいっている企業では、「他者の批判でなければ、何でも自由に書いてよい」くらいにシンプルなルールも多く見られます。
社内のナレッジを集約するのに役立つ社内wikiツールを紹介します。
“社内wikiツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:NotePM公式Webサイト)
12,000社以上の企業の登録実績がある社内wikiツール。高機能エディタと豊富なテンプレートを装備しているため、様々なマニュアル・業務手順書も効率よく作成が可能に。画像編集機能を使えば、手軽に画像へ矢印や吹き出しをつけられる。
作成後の管理・活用のための機能も豊富で、いいね!やコメント機能はもちろん、人気ページランキング、活用している社員の把握といったレポート機能も備える。楽しく情報共有できるのも魅力だ。

(出所:Notion公式Webサイト)
社内wikiに加えて、プロジェクト・タスク管理機能やデータベース機能なども備えた多機能ツール。製品の機能仕様書作成や、企業ルールの共有、ロゴやフォントのカタログ化、営業ノウハウの共有など、あらゆる分野で活用できる。GoogleドライブやFigma、X(旧Twitter)といった多様なアプリを埋め込めるので、プロジェクトのハブとして利用されているケースも。
Markdown対応に加え、写真やURLの追加も可能なので、リッチなドキュメントを作成することが可能だ。

(出所:Qast公式Webサイト)
ナレッジマネジメントに特化したツール。社内wikiはもちろん、「Q&A機能」や「こましりbox」といった、困りごとを可視化してナレッジを引き出す独自の機能を搭載。「社内の誰が・何に詳しいか」を把握しやすいユーザータグ機能によって情報共有を促したり、投稿への拍手といったリアクションが行える称賛機能によって投稿へのモチベーションを向上させたりと、ナレッジ共有を活発化させる仕組みがそろう。
高度な検索性も備え、キーワード検索のほか、タグでの絞り込みやフォルダ分けなどの機能も豊富。添付ファイル内のテキストも検索対象としており、必要な情報へのアクセスを円滑にしている。よく見られている投稿や社員の投稿数だけでなく、アクティブ率や投稿内容の傾向なども分析するダッシュボード機能も用意。効果測定や改善活動も効率化する。

(出所:サイボウズGaroon公式Webサイト)
数千~数万人規模での導入実績が豊富な、大規模向けのグループウェア。社内の様々な情報をポータルや掲示板、ファイル管理などに集約することで、社内wikiとしても使用できる。
アプリケーションの利用権限はユーザー単位、組織単位などで細かく設定が可能。閲覧・編集権限の設定にも対応しているため、「特定の社員のみに公開したい」といったときにも便利。特定のアプリケーションや機能のみを管理するといった設定も行える。大規模組織であっても、システム管理者の負担を軽減しつつ、手軽に使える管理機能が充実している。
kintoneやMicrosoft 365といった他システムともシームレスに連携するのも強み。

(出所:saguroot公式Webサイト)
AIによる横断検索と使いやすいUI/UXを備え、社内に眠る資料を効率的に活用できるナレッジマネジメントツール。従業員規模500名以上の企業向き。
PDF、Word、Excel、PowerPointなどの異なるファイル形式はもちろん、画像内のテキストまで含めて一括で全文検索できるため、必要な情報を素早く見つけ出せる。検索結果には生成AIによる100字程度の要約が自動表示され、ファイルを開かずに目的の情報を直感的に把握可能。検索にかかる時間を削減し、業務の生産性を向上させる。
関連度や掲載日順のソート、AIによる自動タグ付け機能といった便利な機能も充実。ファイルの担当者や関連する知見を持つ人材をネットワーク状に可視化する機能も搭載し、部門を超えた知識共有を促進する。

(出所:Zendesk公式Webサイト)
世界10万社以上で利用されているカスタマーサポートツール。社内wikiとしても活用されている。検索性が高く、情報の取り出しやすさが強み。業務ノウハウやマニュアルの共有を重視したい場合に適している。
編集画面上で、画像や動画を含むコンテンツを簡単に作成可能。「どのコンテンツがどれくらい見られているのか」「どのノウハウ・マニュアルがよく活用されるのか」など、状況分析もカバー。内容に応じて詳しいメンバーに執筆・編集を依頼できる「チームパブリッシング機能」も備え、ツールの活用促進と内容の充実に役立つ。

(出所:Lark公式Webサイト)
チャット、テレビ会議、カレンダー、オンラインドキュメントなど多彩なビジネス機能を搭載。社内外のあらゆるコミュニケーションを一元管理するコラボレーションツール。社内wiki機能も備えており、ドキュメント形式以外にも、シートやマインドマップ、データベースなど、ナレッジを様々な形式で作成・共有する。パーソナライズが可能な優れた検索機能を備えており、目的の情報を探し出すのが容易に。
ユーザーごとに閲覧・編集・コピー・印刷・出力などの権限レベルを割り振れるため、情報漏えいリスクも低減。ナレッジやノウハウの共有だけでなく、社内のコミュニケーション全般の改善を考えている場合におすすめだ。有料版と遜色ない機能群を20ユーザーまで無料で使えるプランを提供している。

(出所:esa公式Webサイト)
不完全なドキュメントでも公開して、チームで楽しく情報を育てるというコンセプトのツール。チャットのように気軽に発信し、情報が育ってきたらwikiのように整理するという仕組みを提供している。
あえて「WIP(書き途中)」と明記して記事を共有する機能によって、アウトプットのハードルを低く設定。そして、複数回の更新を前提としているので、時間をかけてクオリティの高い情報へと育てていける。複数名で情報を育てるための同時編集機能も搭載。Markdownをはじめ、豊富な入力補助機能がそろう。

(出所:Helpfeel Cosense公式Webサイト)
メモ帳のようなライトな入力と充実した分析レポートにより、組織にドキュメント文化を定着させるツール。コンタクトセンターでのマニュアル整備や、研究・開発組織での調査レポート作成といった幅広い分野で活用されている。
単語を[カッコ]で囲むだけでリンク化される機能や、同時編集機能など手軽なアウトプットに役立つ機能が充実。ドラッグ&ドロップやコピペだけで画像や動画、地図の貼り付けも可能だ。
アクセス権はメンバーを限定して付与され、プロジェクトの公開・非公開も行えるため、管理者も安心。Slackとの連携にも対応している。

(出所:shouin+公式Webサイト)
動画・PDFのマニュアルを活用して、限られた予算・時間のなかで人材育成を最適化するeラーニングサービス。自社で作成したマニュアルや、業務手順を撮影した動画をシステム上で共有でき、社内wikiツールとしても活用可能だ。
自社内の用語・ルールを集約する「用語集」や、本部から各店舗に向けた情報発信ができる「タイムライン」といった機能を搭載。「用語集」はキーワード検索、「タイムライン」はタグ付けにそれぞれ対応しており、必要な情報にたどり着きやすい。現場から本部への問い合わせが、約30%減ったという事例も。

(出所:ナレカン公式Webサイト)
高精度検索で社内ナレッジへ即アクセスできるナレッジ管理ツール。生成AI「ナレカンAI」を搭載し、「有給申請の方法を教えてください」など、上司に質問するような感覚でナレッジ検索が可能。登録されたナレッジ内を横断してトータルで最適な回答を自動生成するため、高いヒット率を実現する。複数キーワードやタグ検索、添付ファイル内検索といった検索方法に対応し、個人のスキルを問わず情報に辿りつけるのがうれしい。
データ登録も簡単で、ExcelやPowerPoint、Word、PDF、テキストファイルなどのファイルを添付・アップロードするだけ。AIが内容を解析・要約・重要ポイントを抽出し、すぐにファイルの中身をナレッジとして活用できる。その他、チャットやメールの内容を転送することもできるため、顧客対応の記録や社内外の問合せなどのナレッジデータ化も可能だ。

(出所:Confluence公式Webサイト)
ソフトウェア開発の現場でよく使われている課題管理ツール「Jira」の開発元・アトラシアンが提供。最大の特徴はJiraと連携して利用できること。大企業での利用実績も豊富だ。
業務に関するルールやナレッジの共有のほか、ミーティングの議事録やプロジェクト計画の作成、トピックスへのフィードバックなど、あらゆる情報の集約とコミュニケーションの促進を支援。バージョン管理や変更通知、共有機能、高度な検索機能など、ナレッジ共有のための機能も充実している。

(出所:Qiita:team公式Webサイト)
エンジニアリング関連の情報共有サービス「Qiita」のチーム版。暗黙知をなくし、チーム内の信頼構築にもつながる社内向け情報共有サービス。
Markdown記法で入力でき、入力補助やショートカット機能も用意。テンプレート機能も備えているため、形式を統一したスムーズな情報共有に有用だ。また、グループごとに記事を紐づけてまとめて管理できるため、必要な記事が見つけやすい。共有リンク機能で社外にも共有が可能。
記事にリアクションやコメントも加えられるため、記事に関する議論やフィードバックに役立てられる。SlackやChatworkといった外部サービスとの連携にも対応する。
無料で使い続けられる社内wikiツールを紹介します。

(出所:Knowledge公式Webサイト)
自社サーバーにインストールして利用する、オープンソース型の社内wikiツール。ダウンロードしたファイルを設置するだけで簡単にセットアップができる。
無料ツールながら、モバイル対応、Markdown対応、情報登録やコメントなどのメール・デスクトップ通知、ファイルの添付、キーワード検索機能など、社内wikiツールに求められる機能のほとんどがそろっている。
オープンソースなので、必要な機能を追加することも可能だ。
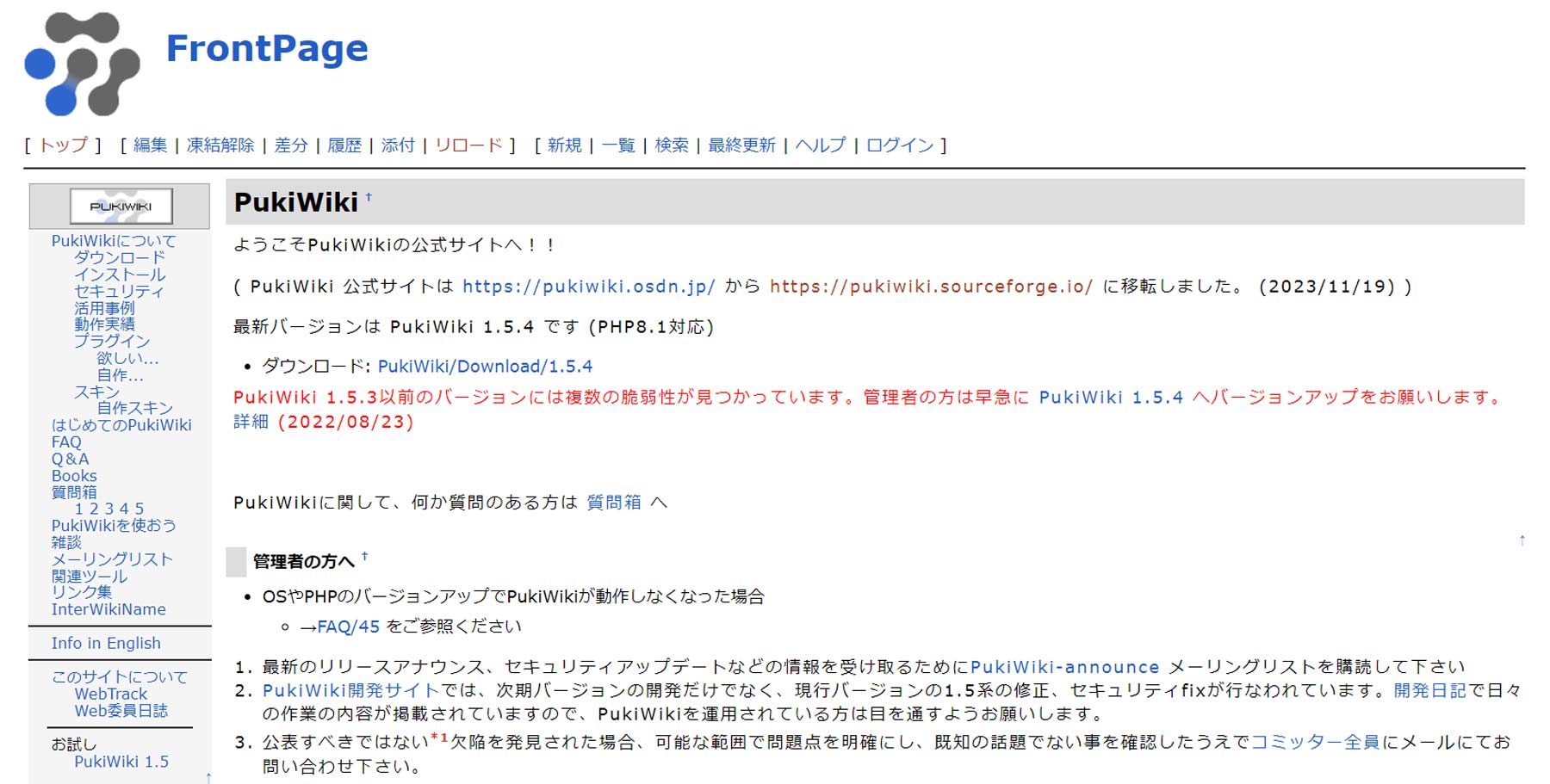
(出所:PukiWiki公式Webサイト)
Webブラウザから自由にページ編集が行えるコンテンツ管理システム。HTMLを使わなくても文字装飾ができるため、手軽なページ作成・編集に役立つ。
YouTube動画の再生プラグインや、ヒント表示付きサイト内検索など、様々な自作プラグインが投稿されており、それらを使って機能を拡張することもできる。ITリテラシーが高い組織に最適だ。
社内の情報共有に課題を感じているものの、「一度チャレンジしたけど、うまく社内に浸透しなかった」という経験を持つ方は少なくないでしょう。社内wikiツールの導入後に活用・定着までしっかり浸透させられれば、様々な効果が期待できます。
導入を成功させるための浸透策としては、以下の4つの方法が挙げられます。
今回紹介した導入時の注意点や社内浸透策などを参考に、社内wikiツールの導入を検討してみてください。
社内wikiツールをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“社内wikiツール”の 一括資料ダウンロードする(無料)
サイボウズ株式会社
中堅企業から大企業まで豊富な導入実績を持つサイボウズのグループウェアです。ITが苦手な人でもわかりやすいUIを搭載。現場職から管理職までスムーズに運用開始できま...
株式会社グッドウェーブ
社内外のあらゆるコミュニケーションを一元化するコラボレーションスイート。チャット、テレビ会議、カレンダー、オンラインドキュメントなどを一つのツールに統合。株式会...
ピーシーフェーズ株式会社
実践重視の研修をオンラインでできるクラウド型eラーニングサービス。学習コンテンツの配信で終わりではなく、確認クイズや実践チェックリスト機能で知識・行動を定着させ...
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。
資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。
なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。