法改正に備えて、JISやWCAGなどの各種規格に則ったWebアクセシビリティ対応を進めたい企業の担当者へ。Webアクセシビリティ診断サービスの種類や料金相場、支援内容の違い、診断方法の選び方について解説します。
Webアクセシビリティ診断サービスは、Webサイトが高齢者や障害者を含むすべてのユーザーにとって、支障なく閲覧・操作できる状態にあるかを確認するためのサービスです。
アクセシビリティの対象は、視覚・聴覚・身体・認知などに制約のある方も含めた幅広いユーザーです。それぞれが必要な情報を適切に取得・操作できる環境が整っているかを多角的に検証します。
診断では、国内のJIS(日本産業規格)が定めた規格「JIS X 8341-3:2016」や、国際的な規格「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」を基準に、サイトの構造や機能がどの程度適合しているかを評価します。これらの基準は、レベルA・AA・AAAといった段階が定められており、レベルに応じた診断を受けられるため、自社の対応状況を客観的に把握可能です。
評価手法には、自動診断ツールによる検査と、専門家による目視でのチェックがあり、サービスによっていずれか、または両方に対応しています。診断の目的は、サイト内の問題点の所在を明らかにし、具体的な改善提案につなげることにあります。
こうした取り組みは、法令対応のためだけでなく、ユーザーの使いやすさ向上や検索エンジン対策(SEO)の観点からも有効であり、Webサイト全体の品質向上につながる重要な施策といえます。
Webアクセシビリティ診断サービスを導入することで、次のようなメリットが得られます。
Webアクセシビリティ診断サービスを導入する最大のメリットは、自社では気づきにくい課題を、専門的な知見を持つ第三者が客観的に洗い出してくれることです。
社内で各ガイドラインを参考にチェックする場合、自社で「何が達成基準に該当するか」「どの程度の対応で十分なのか」といった判断を下すのは難しいものです。社内の担当者のスキルや知識が平準化されていないと、対応のばらつきや見落としが起きやすくなります。
診断サービスでは、JIS X 8341-3:2016やWCAGといった基準を踏まえ、アクセシビリティに精通したコンサルタントや技術者が、ソースコードやUIをチェック項目に沿って検証します。加えて、視覚障害などを持つユーザーによる検証を実施する事業者もあり、実際の利用シーンに即したフィードバックが得られる点も、診断精度の向上に役立ちます。
診断後には、指摘事項の一覧に加えて、改善の優先度や対応方法が整理されたレポートが提供されるため、「どこを、なぜ、どのように直すべきか」が明確になります。対応すべき項目を可視化し、段階的に着手できる体制が整うことも、外部サービスを利用する大きな利点です。
2024年4月に施行された改正障害者差別解消法により、民間企業にも「合理的配慮」の提供が義務づけられました。
これにより、障害者からWebサイトの使いづらさに関する問い合わせや改善の要望が寄せられた場合、企業側は「可能な範囲で対応する義務」を負うことになります。仮に、改善要望に対して何の対応も行わなかった場合、行政指導が入るケースもあり、対外的な信頼を損ないかねません。
こうした法令対応やリスク管理に有効なのが、Webアクセシビリティ診断サービスで取得できる報告書や適合証明書です。
診断サービスでは、診断結果と修正案を整理した報告書や分析レポートが提供され、今後どのような対応が必要かが可視化されます。社内外への説明に活用できるほか、経営層や開発チームなど複数部門での情報共有や、合意形成の促進にも役立ちます。
また、JIS X 8341-3:2016などの基準を満たしたことを示す「適合証明書」が発行されるサービスもあります。
以上のような書面を残しておけば、行政の担当者やWebアクセシビリティへの取り組みをチェックする監査担当者にも説明がしやすく、「社会的責任を果たす企業」であることを対外的に証明できます。
Webアクセシビリティ診断サービスの利用は、Webサイトを訪れるすべての人にとっての「使いやすさ」を高めることにもつながります。
たとえば「文字が見やすく配置されているか」「操作ボタンの位置がわかりやすいサイトになっているか」などの項目を診断。そのうえで、視覚や操作に制限のある方にとってはもちろん、健常者にとってもストレスなく利用できるよう改善方法をアドバイスしてくれます。
また、「見出しの構造が整理されている」「画像に適切な説明(代替テキスト)が付いている」といった、検索エンジンの評価向上につながる項目もあわせて確認するため、SEO対策にも効果的です。
アクセシビリティ対応を通じてサイト全体の品質が高まると、ユーザーの離脱率が下がり、ページの滞在時間増加やコンバージョン率の向上につながります。「情報が探しやすく、誰にとっても使いやすい」と感じられるサイトは、企業の信頼感を高め、サービスや製品に対する好意的な印象を後押しします。
Webアクセシビリティ診断サービスを活用することで、顧客満足度やブランド価値の向上はもちろん、ビジネス成果にもつながるサイトへの改善が期待できます。
Webアクセシビリティ診断サービスは、単にサイトの現状を評価するだけでなく、その後の改善策の提案や、運用支援まで行うのが一般的です。
ここでは、主に提供されているサービスの内容を4つの観点から整理します。
診断サービスではまず、サイトがアクセシビリティの基準にどれだけ適合しているかを確認します。主に使われるのは、日本の基準である「JIS X 8341-3:2016」や、国際的な基準である「WCAG」です。これらの基準では、対応レベルをA・AA・AAAの3段階で評価します。
診断では、Webページの構成や文字の表記、ボタンの操作性などを確認し、どのレベルに達しているかを判定します。調査は、ツールを使って自動的にチェックする方法と、専門家が画面を操作しながら確認する方法を組み合わせるのが一般的です。
更に、実際に視覚障害などのある方がサイトを使ってみて、どこが使いにくいかを確認する「当事者検証」に対応しているサービスもあります。公開前のテストサイトを対象に、事前に診断を行ってくれる事業者もあるため、リニューアルや新規サイト公開のタイミングでも活用できます。
診断では、サイトのどこにどんな使いづらさがあるかを見つけ出すために、様々な観点から細かくチェックが行われます。
検証項目は、「WCAG」の4つの原則に沿って整理されており、「見えるか(知覚可能)」「操作できるか(操作可能)」「内容が理解しやすいか(理解可能)」「どんな環境でも安定して動くか(堅牢性)」という考え方に基づいています。
たとえば、色のコントラストが弱すぎて文字が読みにくくなっていないか、画像に適切な説明文(代替テキスト)がついているか、キーボードだけでメニュー操作ができるか、入力ミスをしたときにエラーメッセージがきちんと表示されるか、といった点を確認します。
そのほかにも、HTMLやJavaScriptなどのコードが正しく書かれているかといった技術的な部分も検証対象です。更に、ロービジョン(弱視)ユーザーへの配慮、音声操作のしやすさ、スマホなどモバイル端末での表示や動作といった観点の検証まで、広く対応しているサービスもあります。
診断の終了後には、結果をまとめたレポートが提供されます。レポートには、サイト上の問題点が整理されており、初めてアクセシビリティに取り組む場合でも現状を把握しやすい仕様です。
たとえば、「画像に代替テキストが設定されていない」「リンクの順序が不自然で操作しづらい」「エラーメッセージが表示されない」といった具体的な指摘が並び、それぞれの影響度や優先順位も示されます。
また、改善に向けたアドバイスも添えられており、どう直せば良いかの方向性が明確になります。診断内容は、開発担当だけでなく、他部門や経営層と共有しやすいように構成されているケースも多く、社内での調整や合意形成をスムーズに進めるうえでも役立つでしょう。
サービスによっては、「適合証明書」や「修正指示書」などの追加資料を発行できる場合もあり、行政対応や監査時の説明資料として活用できます。
Webアクセシビリティ診断は、診断結果を確認して終わりではなく、指摘された項目をどう改善していくかが重要です。
たとえば、サイトを「どのように修正すればよいか」がわかる具体的な修正指示書が発行されるサービスであれば、社内の開発チームで対応をスムーズに進められます。修正に対応できるか不安がある場合は、専門スタッフがHTMLやCSSなどの実装を代行してくれるプランを選ぶと良いでしょう。
修正後には、再診断を通じて改善結果が正しく反映されているかを確認できます。ここで問題が解消されていれば、適合証明書やレベルAA準拠など、公式な記録として残すことも可能です。
また、長期的な運用を見据えた支援メニューを提供している事業者も。たとえば、自社の「アクセシビリティ方針(アクセシビリティ向上のための取り組み、目標などを明記した文書)」の策定をサポートしたり、「自社サイトを更新する際の注意点をまとめた社内マニュアル」の作成を支援したりといった、実務的なフォローも行われます。
加えて、社内の担当者や制作パートナー向けにアクセシビリティに関する研修を実施するサービスもあり、組織全体の理解と対応力を底上げしたい場合に有効です。継続的に対応していくための体制づくりまで支援してもらえることは、社内リソースの限られた企業にとって大きなメリットです。
Webアクセシビリティ診断サービスは、提供形態や診断方法によっていくつかのタイプに分類できます。自社の目的やリソースに応じて、最適なサービスを選定することが重要です。
Webアクセシビリティの課題は、コード上のミスだけでなく、「見づらい」「操作しづらい」といった、使う人の体験に関わる問題も少なくありません。こうした問題は、自動診断ツールだけでは検出が難しく、実際に目で見て、操作して初めて気づけることも多くあります。
そこで注目されているのが、専門家による目視・手動チェックを重視した診断サービスです。このタイプの診断では、専門知識を持つ技術者やコンサルタントが、ガイドラインに沿って実際の画面や操作を確認します。
たとえば、U'eyes Designの「アクセシビリティ対応支援」は、30年以上にわたりユーザー行動を研究してきた実績を背景に、障害当事者による実地テストや行動観察も取り入れた診断を行っています。自社開発の評価ツール「WAIV2」を併用し、技術面とユーザー体験の両面からバランス良く分析できるのが特徴です。
BIPROGYチャレンジド株式会社では、視覚・運動・認知といった多様な障害特性に配慮しながら、民間のアクセシビリティ検査資格を持つチェッカーが、一つひとつの画面を評価します。読み上げソフトでの誤読や、ユーザーがつまずきやすい操作部分を的確に洗い出し、修正の優先順位や背景までレポートに整理してくれます。
また、NTTコム オンラインの診断では、WAIC(Webアクセシビリティ基盤委員会)の委員など専門的な知見を持つコンサルタントが対応。診断後の報告会では、改善方法についての具体的な解説も行われます。
更に、ドーン株式会社では、PCやスマホなど複数のデバイスを用いた実機検証を実施。OSや画面サイズの違いによる表示・操作の差異まで検証されるため、幅広いユーザー環境をカバーした改善が可能です。
アクセシビリティの状態をなるべく早く、手間をかけずに把握したい場合は、自動チェックツールを使った診断サービスが向いています。専用ツールでサイト全体をスキャンし、問題点をスコアや一覧で見える化して整理してくれるのが特徴です。
たとえば、スパイラル アイギス株式会社の場合は、自社開発のツールで1,000ページをわずか50,000円〜チェック可能です。画面の構造や色の使い方、操作のしやすさなども自動的に評価され、問題点の一覧とあわせてスコアで全体の傾向が把握できます。
株式会社先駆の「WEBLY」は、診断が最短1カ月で完了します。納品されるレポートには、アクセシビリティ達成基準との適合状況や数値評価に加え、不適合とされた項目の改善案が一覧化されています。既存のデザインコンセプトをできるだけ崩さない修正内容が提案されており、社内用に編集したうえで、開発担当者や外注先への共有資料としても活用できます。
フォー・クオリアが提供する診断サービスでは、ツールによる自動チェックに加えてソースコードやスクリーンリーダーの動作も個別に確認します。納品されるのは、診断結果の報告書・改善内容を整理したレポート・Webアクセシビリティ方針書の3点セットです。診断から社内報告までをスムーズに進めたい企業にとって、使い勝手のよいサービスです。
Webアクセシビリティ診断だけでなく、アクセシビリティに準拠したサイトの初期構築にも対応するタイプ。
たとえばフレンセルでは、新規のサイトを設計する際、アクセシビリティの観点から要件定義、デザイン、実装の支援を行うサービスを提供しています。あらかじめアクセシビリティに配慮した設計を行っておけば、公開後に大幅な修正を加える必要がなくなるので安心です。
「まずは社内でどこに問題があるのか把握したい」「修正は自分たちで対応したい」という企業には、診断ツールだけを提供しているサービスが向いています。必要なときに自社でチェックできるため、定期的にサイトを見直したい企業や、外注先への指示を都度効率良く出したい企業に適しています。
たとえば、スパイラル プラットフォームの「ISSO®」は、URLを登録するだけで複数ページを一括診断できるツールです。各ページの問題点が、「読み上げ内容の整合性」「視認性」「操作性」などの観点ごとに整理され、スコアもあわせて表示されるため、優先順位を付けて対応できます。
Webアクセシビリティ診断サービスの料金は、診断方法や対象ページ数、診断範囲、更には診断後の支援内容などによって大きく異なります。
以下では、一般的な価格帯や費用に影響する要因、具体的な提供事業者の事例を紹介します。
Webアクセシビリティ診断の費用は、診断方法や支援内容、対象ページ数によって幅があります。以下では、よくあるプランの価格帯をタイプ別に整理しました。
簡易診断の場合、自動チェックツールを用いて診断を行うサービスが多く、料金は10ページあたり5万円〜20万円前後です。対象は数ページ程度に限定され、レポートもエラーの一覧やスコアの提示など、簡素な形式となっています。
JIS X 8341-3:2016に準拠した手動診断の料金は、10ページあたり20万〜30万円前後かかります。このプランでは、専門家による目視チェックに加え、課題の整理や優先順位を明記した改善提案などが含まれるため、実際の対応にもつなげやすくなっています。
改善提案書の作成や修正方針の提示、再診断、適合証明書の発行といったサポートがセットになったプランでは、40万円以上を想定しておくと安心です。内容に見合った支援が含まれているケースが多く、しっかり改善を進めたい企業にとっては有効な選択肢です。
後から診断対象を追加したり、修正後に再診断を依頼する場合は、3万〜10万円前後の追加費用がかかることもあります。状況に応じて、段階的に利用することも検討できます。
このように、診断内容の範囲や支援レベルによって料金には差が生じます。対応状況の確認だけで十分か、改善支援も受けたいのか、自社の目的やリソースに応じて、適切なプランを選ぶことが重要です。
診断サービスの料金は一律ではなく、いくつかの要因によって大きく変動します。ここでは、費用に影響を与える主なポイントを整理して紹介します。
アクセシビリティ診断の費用の変動にもっとも大きく影響するのは「診断するページ数」です。たとえば、10ページだけ診断する場合と、100ページを対象にする場合とでは、必要な作業量が大きく変わるため、それに応じて費用も変わります。
「どのレベルまで対応するか」もポイントです。アクセシビリティの基準は「A・AA・AAA」の3段階あり、高いレベルを目指すほどチェックの内容が複雑化し、コストも上がる傾向にあります。
自動ツールだけを使う簡易的な診断なのか、人の目によるチェックも含まれるのかによって、料金は変わってきます。そのほか、診断の内容が「現状把握だけ」なのか、「改善案の提案」や「修正作業のサポート」「再診断」「適合証明書の発行」などを含むかどうかによっても、金額に差が出ます。
そのほか、障害当事者による実際の検証や、社内研修といったオプションを追加する場合も、費用が上乗せされます。
このように、診断内容や診断レベル、オプションの有無によって料金は大きく変動するため、目的や予算に応じてプランを選ぶことが大切です。
アクセシビリティ診断サービスは、対応内容や支援の範囲によって料金が大きく異なります。以下に、3社の料金プランを掲載したので参考にしてみてください。
| 事業者名 | タイプ | プラン名 | 診断 方法 |
ページ数 目安 |
主な支援 内容 |
価格 (税込) |
納期 目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPROGYチャレンジド | 目視・手動チェックに強み | スターター | 自動診断 | 10ページ〜 | 基本診断、報告書、簡易アドバイス | 17万円〜 | 約1週間 |
| ライト | 自動診断 | 10ページ〜 | スターターコースの内容 + 分析レポート、修正方針の提示、報告会の実施 |
22万円〜 | 約2週間 | ||
| スタンダード | 自動+手動 | 10ページ〜 | ライトコースの内容 + 検査証明書、再診断 |
27万5,000円〜 | 約3週間 | ||
| プレミアム | 自動+手動+改善支援 | 10ページ〜 | スタンダードコースの内容 + 適合証明書、方針書作成支援 |
32万5,000円〜 | 約1.5カ月(要相談) | ||
| NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション | 目視・手動チェックに強み | スタンダード | 自動診断 | 100ページ | 基本診断、問題点解説 | 27万円 | 約2週間 |
| プレミアム | 自動+手動 | 10ページ | 基本診断、問題点解説、修正案の提示 | 30万円 | 約3週間 | ||
| スパイラル アイギス | チェック・検証の効率化に強み | Webアクセシビリティ診断サービス | 自動診断 | 最大1,000ページ | 基本診断、問題点一覧・スコア付きレポート | 50,000円〜 | 最短5営業日〜 |

(出所:アクセシビリティ対応支援公式Webサイト)
30年以上ユーザーの行動を観察・研究してきた知見を活かし、障害当事者・健常者ともに使いやすいWebサイトの設計を支援するサービス。自社開発の自動評価ツール「WAIV2」による調査とあわせ、障害当事者や高齢者によるユーザーテストと行動観察、体験談の聞き取りといった実地調査も行う。
技術的な評価としては、スクリーンリーダーの利用状況、操作時の身体的負担、表示理解のしやすさなどを分析し、開発中の画面やコードに対して修正案を一覧で提示する。
更に、ユーザーの行動心理の分析結果をもとにしたシナリオやカスタマージャーニーマップの作成も可能。実際に操作した時の負荷やわかりやすさを検証して提示する資料のため、ユーザーにとって使いづらいUI/UXの改善に役立てられる。
これらの診断を通して、アクセシビリティ規格への準拠だけでなく、ユーザー満足度やLTVの向上にも寄与する開発・マーケティングのヒントが得られる。

(出所:Webアクセシビリティ診断公式Webサイト)
レポートの質と検証体制にこだわり、官公庁や多岐にわたる業種の企業で導入されているサービス。診断は自動ツールに加え、専門家が各画面の操作のしやすさを目視・手動で検証する。こうした人の判断を伴う工程により、操作性の不備など機械だけでは見つけにくい問題を洗い出す。
報告書には、診断結果の一覧に加え、問題の背景や原因、修正の優先度や修正案までが記載される。希望すれば「適合証明書」の発行も可能で、行政機関の担当者や上場企業の内部監査担当者に、アクセシビリティに真摯に取り組んでいることを示せる。
プランは全4種。基本項目のチェックを行うスタータープランや、リアルシチュエーションに即したユーザーテストを実施し、改善提案を行うプレミアムプランなどを用意。診断報告をもとに、迅速にサイトの改善をしたい企業や、多様な障害特性への配慮が特に求められる教育・医療・福祉関連事業者に向いている。

(出所:Webアクセシビリティ診断公式Webサイト)
自動ツール診断とあわせ、アクセシビリティ分野の専門知見を持つWAIC委員のコンサルタントが手動で検証を行うサービス。
プランは2種類あり、プレミアムプランは手動診断付きで、JIS規格で定められたレベルAAに準拠した診断が可能。診断後のレポートには、問題点の解説に加えて具体的な修正方法が記載されており、改修作業に活用できる。コストを抑えたい企業はスタンダードプランの選択がおすすめ。ツールを用いて100ページまで自動診断を行う。
報告会はオンライン形式で実施。コンサルタントが具体的な改善例を挙げながら解説するため、社内への理解や関係者との情報共有がスムーズに進む。オプションで、障害当事者によるユーザー調査や、Webアクセシビリティ方針ページの原案作成、アクセシビリティ理解度を深める社内研修なども提供している。
JIS適合を目指す企業や、第三者の評価をもとにサイトを改善したい運営者におすすめ。

(出所:ウェブアクセシビリティ診断サービス公式Webサイト)
Windows・Mac・iOS・Androidの各デバイスで実際にサイトの画面を操作しながら確認する実機検証を取り入れたサービス。様々なデバイスで多角的に検証することで、異なる環境での表示・操作性の差異や、特定のOSで発生する不具合を事前に検知。どのユーザー環境でも安定したアクセシビリティを実現できる。
診断結果には修正すべき箇所の指摘に加え、フロントエンド実務経験を持つエンジニアが作成した、コードレベルでの具体的な修正方法を記載。制作担当者は迷うことなく実装作業に着手できる。依頼の際は、診断ページの選定からレポート作成、Webアクセシビリティ方針ページの納品まで一括で任せられる。
限られたリソースで確実かつ効率的に対応を進めたい企業や、大規模で複雑な構造のサイトを運営する企業にもおすすめ。

(出所:Webアクセシビリティ診断サービス公式Webサイト)
自動ツール診断と目視での確認を組み合わせ、効率と対応力を両立したサービス。国内JIS規格やWCAG2.1に対応。大規模サイトであっても全ページの自動診断を前提とし、全体の傾向を把握できる。
評価対象は、知覚・操作・理解・堅牢性といった主要項目に加え、コントラストや文字サイズなど視覚バリアフリーの観点も網羅。サイトのコーディング前段階でのデザインに対する診断にも対応し、実装前からアクセシビリティの課題をつかめる。レポートは、スコア化された診断結果や問題点の一覧、エラーの頻出傾向と修正アドバイスをまとめて提示する。
アクセシビリティ準拠度合いを簡易的にスコア化するライトなサービスや、サイトの修正指針、検査証明書を含む適合検査プランなど3種類を用意。診断後の修正代行、Webアクセシビリティ方針ページの原案作成も依頼可能だ。リーズナブルかつ効率よく問題点を可視化したい企業に適している。

(出所:Webアクセシビリティ診断公式Webサイト)
診断範囲・診断手法の柔軟性に優れ、公開前後を問わずあらゆるWebサイトのアクセシビリティ診断を実施できるサービス。JIS X 8341-3:2016やWCAG 2.2などの国内外ガイドラインに対応し、ツールを用いたクイック診断と、専門エンジニアによる目視を伴うスタンダード診断の2種類を用意している。
診断では、Webサイト全体を自動巡回してアクセシビリティの問題を検出。複数ドメインで構成されたサイトにも対応し、リンクの先までたどって検証を行う。レポートには問題箇所のキャプチャと図解による解説に加え、改善策も網羅しているため、社内説明資料としても活用できる。報告会や説明会の開催も可能で、現場レベルから意思決定層まで組織内での理解浸透に役立つ。
運用負荷を抑えながら組織全体のアクセシビリティ水準を底上げしたい企業や、社内の説明資料として使える画像付きレポートが必要な場合におすすめ。

(出所:WEBLY公式Webサイト)
診断から再検査、証明書発行、結果報告会実施まで一貫して対応するサービス。自動ツールの活用により、最短1カ月という短納期で診断を完了できるのが特徴だ。
診断工程ではコンテンツの構造・コントラスト・操作性・理解のしやすさなどを総合的にチェック。診断結果は、問題点と改善案をページごとにまとめて提供する。たとえば現状のテキストコントラスト比と、基準としたいテキストコントラスト比が数値で示されるうえ、対応基準に満たない箇所に対しては具体的な修正案を提示。図解や説明文も付いており、Webサイトの開発担当者・外部制作パートナー・経営層にとっても理解しやすい構成となっている。
また、Webアクセシビリティ方針の策定支援や、ガイドラインへの準拠宣言などの作成も可能。更に、診断完了後の改善作業のサポートや再診断にも対応しており、診断後のフォローアップを求める企業に向いている。

(出所:ウェブアクセシビリティ診断公式Webサイト)
JIS X 8341-3:2016に準拠した診断が、最短7営業日で完了するサービス。自動診断と、ソースコード、スクリーンリーダーの確認を行い、サイトの構造・視認性・操作性・多様なデバイスでの表示まで幅広く検証する。診断に対応するページは最大40ページ。サイトのテンプレート数や構造に応じて必要な診断範囲を見積もる方式のため、コストの見通しが立てやすい。同社のスタッフとのヒアリングを通じて、診断範囲と適合レベルを柔軟に設定できる。
成果物は、診断結果報告書、診断レポート、Webアクセシビリティ方針書の3点セット。不適合箇所の改修支援や再診断にもオプションで対応しており、診断結果の活用から実行フェーズまでスムーズに移行できる。
義務化された法令に対応するにあたって発生する課題を短期間でクリアし、イメージ維持をはかりたい企業に適している。

(出所:Webアクセシビリティ対応支援公式Webサイト)
初期診断から改善支援、再診断までワンストップで対応するサービス。Webアクセシビリティへの対応レベルに応じて、「配慮」「一部準拠」「準拠」を目指す3種類のプランを提供。配慮レベルを目指すプランは、最短3営業日で診断できる。自動診断ツールを用いて10ページまでを対象にチェックを行い、達成基準リストと簡易レポートを提供。初めてアクセシビリティ診断を活用する企業に適している。
一部準拠を目指すプランでは、診断ツールと専門家のダブルチェックを実施。課題の背景や改善策を含めた詳細レポートを提供するため、具体的な改善施策を求める企業に向いている。準拠を目指すプランでは、サイトの改善支援も実施。アクセシビリティに本格的に対応していきたい企業におすすめだ。
一年以内に追加の診断依頼をした場合、10%の割引を適用。まずはスモールスタートして段階的に対応範囲を広げたい企業に適している。
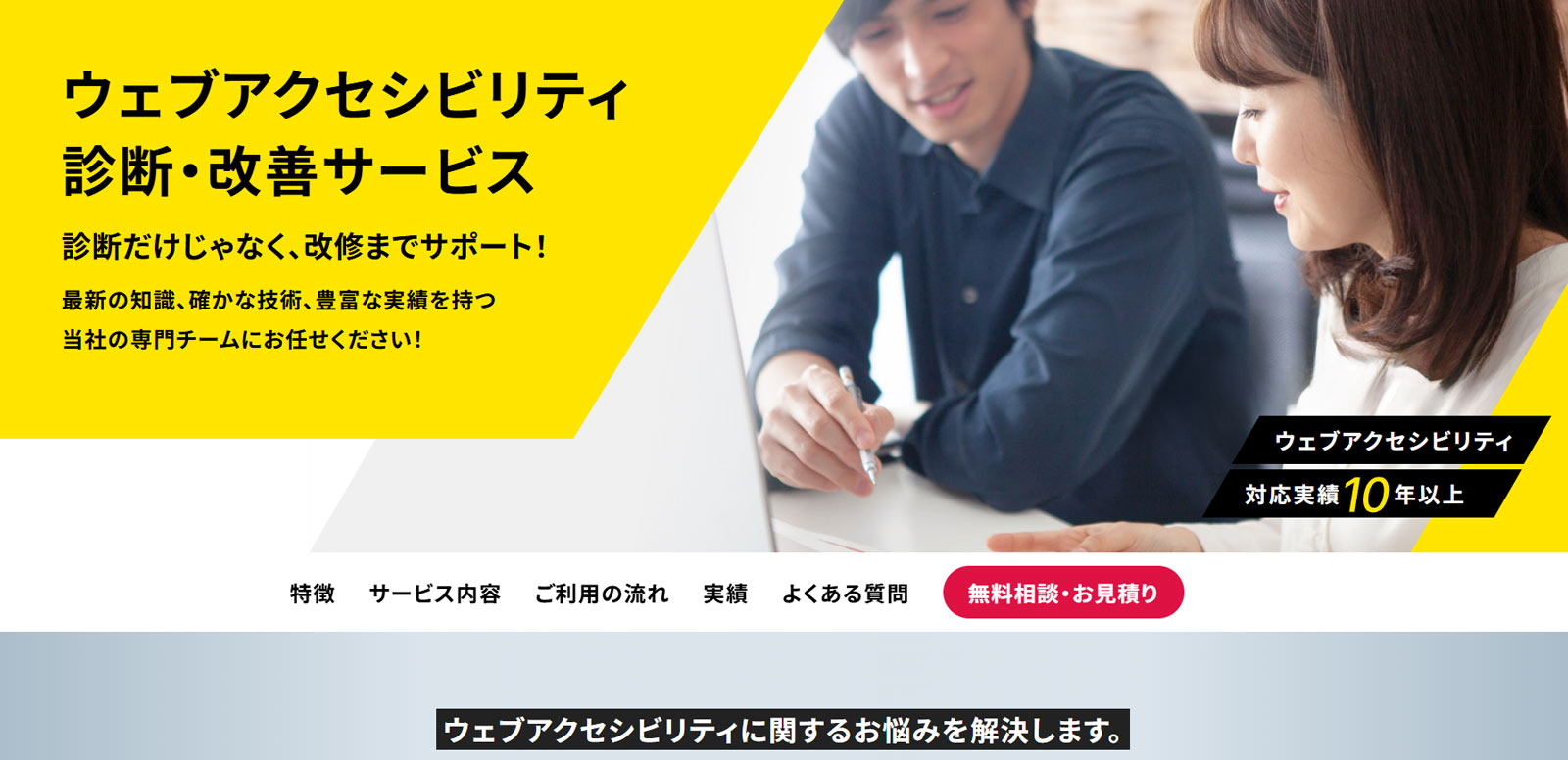
(出所:Webアクセシビリティ診断・改善サービス公式Webサイト)
Webアクセシビリティ診断からサイトの改善提案をはじめ、アクセシビリティの視点を取り入れたサイトの初期構築まで一貫して対応するサービス。JIS X 8341-3:2016レベルA・AAへの適合を前提に、ソースコードの診断や音声読み上げソフトを使った診断、コントラストチェックなど多角的な診断を行う。
診断後は、オンラインによる報告を実施。別途料金で、改善提案指示書の作成や改修後の再診断を依頼できる。
また、新規サイト設計時に、アクセシビリティの観点から要件定義、デザイン、実装の支援を行うサービスを提供。あらかじめアクセシビリティに配慮した設計を行っておけば、公開後に大幅な修正を加える必要がなくなるので安心だ。

(出所:Webアクセシビリティ診断・UI検証ツール ISSO®公式Webサイト)
Webアクセシビリティ診断を中心に、UIの改善やSEO対策にも役立てられるツール。診断は、URLを登録するだけで自動で実行され、大量のページを一括検証可能。結果はページごとに100点満点のスコアで表示され、スコアの低いページを優先度の高い改善箇所として特定できる。
検証は音声ブラウザを想定した「音声ユーザビリティ」と、色覚や視覚バリアフリーに対応する「文字ユーザビリティ」の観点で実施。読み上げ内容の整合性や操作性、情報の理解しやすさといった観点から問題箇所を抽出する。検出結果は「エラー」「警告」「要判断」「手動確認」の4つの基準で分類され、開発チームや外注先へのフィードバックにも活用できる。そのほか、SEO対策に役立つ機能としては、テキストの表記ゆれ検出や、サイトマップの自動生成などがある。
検証業務を内製化したい企業や、委託先から上がってきた成果物の品質を定量的に評価したい企業におすすめ。
2024年の法改正を受けて、Webアクセシビリティへの対応は「企業の努力目標」から「社会的責任」へと変わりつつあります。特に行政機関や上場企業では、JIS X 8341-3:2016に準拠した検証や、第三者が発行する適合証明書の取得が求められる場面も増えています。
そこで役立つのが、Webアクセシビリティ診断サービスです。現状把握に特化した簡易診断サービスから、改善提案・再診断・証明書発行などを含む本格的なサービスまで、目的や体制に応じた様々なタイプがあります。費用も50,000円程度の手軽なプランから、30万円以上の本格支援を行うプランまで幅広く用意されています。
また、価格とあわせて「自社にとって必要な支援内容がそろっているか」「社内で決めた対応方針に合っているか」という視点でサービスを選ぶことも重要です。まずは少ないページからの診断を入口に、状況に応じて改善支援や再診断へと広げていくことも、効果的なサービスの取り入れ方といえるでしょう。
Webアクセシビリティへの取り組みは、単なるチェック作業ではなく、企業価値を高める重要な一歩です。ユーザーにとって使いやすいサイトづくりの基盤として、診断サービスの活用をぜひ検討してみてください。
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。
資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。
なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。