最新法令に対応した社内規程の作成や管理を効率化したい、法務・管理部門担当者や、社労士の方へ。規程管理システムのメリットや比較ポイントについて解説し、AIを活用したクラウド型のツールを含め、タイプ別におすすめサービスを紹介します。
“規程管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
規程管理システムとは、各企業が独自に定める社内ルール「社内規程」の作成・校正・管理を行うためのシステムのことです。
AIを搭載したシステムも多く、情報収集や法令チェック、新規規程作成、改訂作業の効率化が可能。クラウド上でドキュメントや履歴を一元管理できるため、コンプライアンスやガバナンスの強化にもつながります。
企業には様々な規定が存在します。中には、就業規則や賃金規程、個人情報管理規程など法令に沿った運用が必要な項目が多くあり、これらは関係法令が改正されたら、その都度、変更しなければなりません。しかし、規程が多い場合や、法改正が頻繁に行われるような場合は負担が大きくなりがち。「改訂もれ」「記載ミス」などの課題も挙げられます。
これらの負担・ミスを防止して、社内規程に関する各種業務を効率化してくれるのが規程管理システムです。
| ユーザー企業向け | 作成・レビュー・管理に強み |
|
|---|---|---|
| 汎用的な文書管理ができる |
|
|
| 社労士向け | 規程の作成・共有に強み |
|
「すぐにサービス選定に移りたい」という方は、以下のリンクから各サービスの紹介をご覧ください。「もう少し概要を詳しく知りたい」という方は、このまま読み進めてください。規程管理システムの主な機能や導入メリット、比較ポイントなどをご紹介しています。
おすすめの規程管理システム(作成・レビュー・管理に強み)
おすすめの規程管理システム(汎用的な文書管理)
おすすめの規程管理システム(社労士向け)
規程管理システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“規程管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
規程管理システムは、主に以下のような機能を搭載しています。規定の作成から編集・改定、管理、公開まで、一連の業務負担を大幅に軽減できます。
| 雛形による作成 | テンプレートを利用して各種規定を簡単作成。中には、解説をつけられる機能を搭載したものも |
|---|---|
| 編集・改定 | クラウド上で複数人での編集が可能。インデント調整などで改定時の編集作業も効率化 |
| AI校正 | 過去規定との比較、表記ゆれ、条ずれなどの自動チェックで、確認負担を軽減 |
| 改訂履歴管理 | バージョンごとに改訂履歴を時系列で表示。新旧対照表の自動出力に対応していれば、比較やチェックが更に容易に |
| Web公開 | 周知や配布に手間がかからない。タイマー設定による公開の自動化も |
| 検索機能 | 体系・50音・全文検索が可能。AIサジェストに対応したものもあり、目的の規定を迅速に見つけられる |
| リスク検知 | AIを活用して、リスクの見落としや必要条文の抜けもれを防げる |
上記のような機能により、規程管理システムを導入することで得られる、4つのメリットについて解説します。
一から社内規程を作成しようとすると、情報収集や内容の検討など調査・準備にも工数がかかり、担当者の大きな負担になります。
Web上で公開されている雛形をベースにしたり、社労士に雛形を用意してもらったりする場合でも、自社の規定に則した雛形を見つけられずに苦労することは少なくありません。そのほか、体裁や書式など社内にあわせたフォーマットに整えるのも手間がかかります。
その点、規程管理システムなら、システムに搭載された雛形を使ったり、設問に答えるだけで規程が自動作成されたりと作成過程を効率化できます。
経験の少ない担当者でも、雛形や自動作成機能を活用することで、一定水準をクリアした規程を作成できます。コメントを付与した上でのバージョン管理に対応したツールも多く、業務の属人化を防ぐとともに、レビューフローの改善にも効果的です。
また、AIによる校正機能を搭載しているシステムなら、表記揺れや文言抜けもれ、法令違反の防止に役立ちます。
これまでは最新法令に対応するために、改正内容を理解してから更新・変更をする必要がありました。しかし、規程管理システムを使えば、解説付き雛形と比較することで、効率的な更新・変更が可能になります。
また、就業規則に影響を及ぼす法改正情報をリアルタイムでキャッチし、規定改定のポイントとともに配信してくれるサービスもあります。
規程の数や更新回数が増えるほどに、「いつ何をどう改訂したのか」「どれが最新版なのか」のように管理負担も増していきます。そのため、規程管理システムで改訂履歴を保存・管理するのが効率的です。「新旧対照表」を自動作成できれば、関連部署への説明や社内での規定変更周知の作業が楽になります。
また、社内間や企業と社労士との間で、改訂作業の過程を共有できるタイプのシステムなら、関係各所とのコミュニケーションの円滑化にも役立つでしょう。
規程管理システムは、大きく、企業の法務部が自社内で使うタイプと、社労士が顧問先の規程業務に使うタイプに分けられます。更に、企業向けのタイプは、規程管理に特化したタイプと文書管理全般に汎用的に使えるタイプに分けられます。
| ユーザー企業向け | (1)作成・レビュー・管理にも強みのあるタイプ |
|---|---|
| (2)汎用的な文書管理ができるタイプ | |
| 社労士向け | (3)規程の作成・共有に強みのあるタイプ |
それぞれのタイプについて解説します。
社内規程に加えて、契約書の作成・レビュー・管理もひとつのシステムで行えるタイプです。これらの社内規程管理システムは、「就業規則」「賃金規定」「賞与規程」といった社内規程に関するテンプレートが用意されており、効率的な規定作成が可能。「テレワーク勤務規程」「ソーシャルメディア利用規定」といった最新の規程雛形もあります。
また、これらのタイプはAIを活用して「LAWGUE」や「LegalOn」のような契約書レビューや、「KiteRa Biz」の規程の法改正レビューに対応している製品も多いです。チェックの効率化を同時に進めたい場合にも適しています。
社内規程に限らず、契約書、議事録、報告書、稟議書など様々なオフィス文書の管理も効率化したい場合に有効なタイプ。汎用的な文書管理ができるタイプは、新旧比較、改訂管理、全文検索といった機能が搭載されており、文書管理を効率化してくれます。
こちらのタイプに該当する「楽々Document Plus」では、バックオフィスや営業部門のほか、開発・製造・品質管理部門や研究部門といった、ページ数が膨大にある文書の管理・活用にも強みを持ちます。また、「OPTiM 文書管理」は、AIが非定型文書から台帳を自動作成し、全文検索や期限通知が可能。手書き文字や図面を含む多様な文書の一元管理が特徴です。
企業から社内規程の作成や改訂を依頼される社労士の方にとって便利なのがこのタイプです。規程の自動作成や規程に特化したエディター機能で効率的な作成を支援。規程データをクラウドで管理・共有できるので、コメント欄で意見のやり取りをしたり、疑問点にマーカーを入れたりするなど、顧客企業とのコミュニケーションが円滑になります。
「規程管理システム PSR社労士版」では、顧問先5企業まで・1社ごとに6規程(全30規程)まで登録可能となっており、顧問先ごとへの支援内容のバラツキを防いで、コンサル業務の標準化をはかれます。
前述のタイプを前提に、自社にあった規程管理システムを選ぶ上でチェックすべき、比較ポイントを解説します。
搭載されている雛形の種類はシステムによって異なります。規程を新規作成することが多い現場では、雛形の種類の充実度も業務効率化のポイントに。たとえば、「LegalOn」は「情報セキュリティ管理規程」や「スキャナによる電子化保存規程」といった雛形が。社労士向けの「スマート規程管理」では、「安全衛生管理規程」や「ストレスチェック制度実施規程」などの90種類以上に対応しています。
ただし、自社特有の規程の種類が多い場合は、雛形の種類だけでなく、新規程や自社テンプレートの作りやすさを重視してもよいでしょう。
規程を作成する際、専門書の参照・リサーチが欠かせません。しかし、アナログベースの調べものは担当者の負荷になります。この点については、解説を参照しながら編集できる機能や、法令出版の解説付き雛形と連携できる機能、文書のレビュー結果として解説文を表示する機能が搭載されているシステムの活用が便利です。
たとえば「LAWGUE」では法改正の影響のある文書を自動で特定するとともに、改正内容を表示できるようにしています。「スマート規程管理」はシステム上で新日本法規出版が提供する規程の条項検索や確認も可能です。
規程管理だけなく、契約書全般の作成・管理を行いたい場合は、雛形からの作成機能、レビュー機能、検索機能などを持つシステムが適しています。雛形の搭載、AIによるレビュー、過去契約書との比較といった作成補助機能、バージョン管理やコメント付与などの管理機能が充実しているものがおすすめです。
社内規程の作成やレビュー、管理にも強みのある規程管理ツールをご紹介します。
| サービス名 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|
| LAWGUE | 解説付きの雛形集による規程作成や、新旧対照表の出力に対応 | 要問い合わせ |
| LegalOn | AIによる契約書レビュー機能が充実。雛形を用いた社内規程の作成も可能 | 要問い合わせ |
| KiteRa Biz | 設問に回答して規程を自動生成でき、ひな型も200点と豊富で作成・編集に強み | 要問い合わせ |
| 規程管理システム(システム ディ) | 各種規程の作成だけでなく廃止まで効率化。カスタマイズ性も高い | 要問い合わせ |
“規程管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:LAWGUE公式Webサイト)
社内規程や契約書をはじめとした文書の作成・レビュー・管理などを効率化するクラウド管理サービス。規程管理では、解説付きの雛形集を用いて新しい規程を作成することができる。最新の法令に合わせた校正にも対応(法令出版社の雛形の搭載はオプション)。
改訂履歴は自動保存され、新旧対照表も出力できるので、「どこが変わったのか」「どれが最新版か」を確認しやすい。インデントや参照条文番号のズレ、表記揺れアラート機能といった文書作成のサポート機能、AI OCRによる文字認識、類似した文章や条項の検索も役立つ。
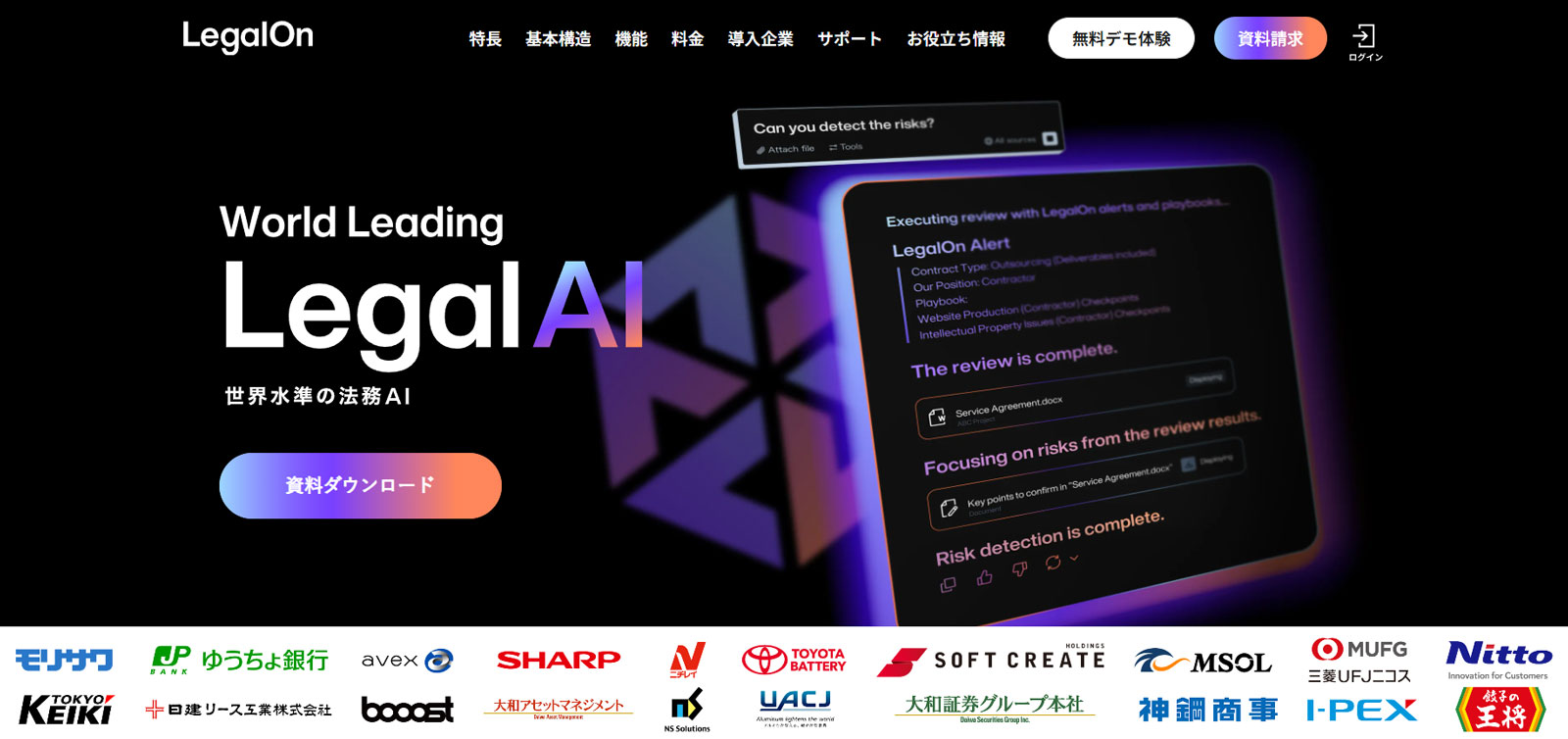
(出所:LegalOn公式Webサイト)
案件管理や契約審査、契約管理といった多様な法務業務をAIでサポートする法務支援プラットフォーム。弁護士監修の豊富なテンプレートには、規約や社内書式も含まれ、作成補助機能や文書管理機能も備えているため、規程管理にも対応できる。
レビュー(契約審査)やコントラクトマネジメント(契約管理)、マターマネジメント(案件管理)などの業務に特化したモジュールを追加でき、同一プラットフォーム上で効率的に実行可能。契約書編集に特化したオンラインエディターでの校正サポートや、AIによる契約書情報の自動抽出、横断検索、バージョン管理、柔軟なアクセス権限設定など、法務業務を多角的にサポートする。

(出所:KiteRa Biz公式Webサイト)
規程管理業務の中でも、特に作成と編集に強みを持つ規程効率化サービス。作成から管理・周知・電子申請まで一連の工程を網羅したシステムで、規程業務の大幅な効率化とコーポレートガバナンスの強化を実現する。関連会社分も横断管理して、グループ全体での情報共有も可能だ。
200種類以上ある弁護士・社労士監修のひな型の活用や、設問に回答する自動ガイドで一定水準を満たす企業の状況に合わせて効率よく規程作成できる。最新の法改正・条項の欠落チェック対応のAIレビュー機能も搭載し、確認が必要な条文のピックアップと参考条文をもとにワンクリックで反映して、対応漏れのリスクを軽減する。
そのほか、新旧対照表の自動生成、従業員の問い合わせ対応を軽減するQ&Aアシスタント機能で規程の運用もサポートする。

(出所:規程管理システム公式Webサイト)
各種規程の作成から廃止まで、規程管理における一連のフェーズの業務効率化機能を備えたシステム。規程を閲覧・活用する従業員や、改訂・管理を担当する法務部門など、それぞれの立場に沿った課題を解決できる仕組み。新旧対照表の管理などができる「管理機能」、Wordからの取り込みや規程雛形を備えた「作成機能」、文字校正や法改正(オプション)に対応する「改訂機能」、最新規程の公開日の設定・承認を行える「公開・閲覧機能」で構成されている。
拡張性やカスタマイズ性に優れ、他社システムとの連携やグループでの利用や規程以外の文書管理にも利用もしやすい。
汎用的な文書管理に強みのあるツールを紹介します。
| サービス名 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|
| 楽々Document Plus | 全文検索、文書同士のリンク付け、契約書の期限通知など管理機能が充実 | 月額90,000円/100ユーザー(クラウド版) |
| OPTiM 文書管理 | 文書をアップロードするだけで、AIが非定型・定型問わず重要情報を自動抽出 | 要問い合わせ |
| リコー ドキュメントライフサイクルサービスSelect | 社内規定や契約書以外の様々な文書に対応し、メンテナンス支援も提供 | 要問い合わせ |
| 規程管理システム(システムギア) | 規程だけでなく、マニュアル・ISO文書など、あらゆる社内文書を一元管理 | 要問い合わせ |
| DocLAN®︎ | Word等の文書を自動でHTML変換し、Web公開・閲覧を効率化 | 要問い合わせ |
“規程管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:楽々Document Plus公式Webサイト)
社内規程や契約書のほか、ISO文書などの様々な文書をシステム上で一括管理できる文書管理・情報共有システム。契約書管理では、自動通知・更新などの期限管理機能により、更新手続き忘れ等の業務ミスを防止。契約更新時も承認ワークフロー設定や、契約先、契約内容による検索や版管理も可能。文書同士のリンク付け、全文検索、旧文書との変更点比較、作業履歴とアクセスログなどの機能が充実。
紙で保管していた文書を電子化できるので、ペーパーレス化や電子帳簿保存法にも対応。文書へのアクセス管理、印刷・持ち出し制御といったセキュリティ対策機能も揃っている。

(出所:OPTiM 文書管理公式Webサイト)
AIを活用して、社内規程・議事録・稟議書・マニュアル・図面といった多様な文書を一元管理するサービス。文書をアップロードするだけで、AIが非定型・定型問わず重要情報を自動抽出し、管理台帳を自動作成する点に強みを持つ。手書き文字や低解像度データ、更には画像データやDocuWorks文書にも高精度で対応し、AI解析・データ保管・検索が可能だ。また、OCR処理された画像ファイルを含む文書内の全文検索や、有効期限の自動通知機能により、文書管理の工数とリスクを大幅に削減。部署・役職ごとのアクセス権限設定など、セキュリティ対策が充実しているのも安心。

(出所:リコー ドキュメントライフサイクルサービスSelect公式Webサイト)
重要文書の電子データ化とクラウド版の文書管理などをセットで提供するリコーグループによる文書管理サービス。ツールの導入だけでなく、データベースの運用・管理などメンテナンス支援もしてもらいたい企業におすすめ。議事録やマニュアル、ISO関連書類など、会社規定書類や契約書以外の文書管理にも広く対応。契約書の共有化と台帳管理にも対応しており、社労士と連携した活用にも向いている。
スキャニングや保管、満了時の処理まで、運用パートナーとして全面的にサポート。契約書管理を通じて、働き方改革にも貢献する。

(出所:規程管理システム公式Webサイト)
規程からマニュアル・ISO文書までを一元管理する規程管理システム。ブラウザ閲覧と全文検索を備え、最新版周知や改訂経緯の共有を容易に。インデント統一、条項番号自動付番、表記ゆれチェックを標準装備し、新旧対照表もワンクリックで生成できるため、改定作業の手間を大幅に削減可能。更に、公開タイマーやグループ別公開、詳細な権限設定により、稟議後の自動公開や部署限定周知にも対応するため、ガバナンスを強化できる。一般企業はもちろん、金融機関や学校法人などでの管理におすすめ。最短3カ月で本稼働という導入スピードも心強い。

(出所:DocLAN®︎公式Webサイト)
社内規程やマニュアル、ISO文書の作成からWeb公開までを一元管理できる文書管理システム。WordやExcelで作成した文書を取り込むだけで、自動的にHTML形式へ変換し、イントラネット上でスムーズに閲覧できる環境を構築する。
専用の閲覧ソフトを必要とせず、ブラウザ上で本をめくるような感覚で文書を確認できる点が特徴。目次の自動生成や文書間のリンク設定も自動で行われるため、読み手は目的の情報へ迷わずに到達できる。更に、管理者も既存のファイル形式のまま登録作業を行えるため、HTML化への専門知識は不要。厳格な版管理機能により、いつ誰が改訂したかという履歴を確実に記録し、新旧対照表も容易に作成可能。承認ワークフロー機能も標準搭載し、作成から承認、公開までのプロセスをシステム内で完結させる。
社労士事務所向けの機能を備えたツールをご紹介します。
| サービス名 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|
| 就業規則ナビ | 「KING OF TIME」関連サービス。アンケートに回答するだけで、簡単に就業規則・給与規程を作成可能 | 要問い合わせ |
| スマート規程管理 by LAWGUE | AIによる条番号の自動補正や表記ゆれの検出で、入力作業を効率化 | 要問い合わせ |
| 規程管理システム PSR社労士版 | オリジナルの雛形が充実。法改正に伴い改訂が必要な規程を自動通知 | 月額7,000円~(基本パックプラン・一般向け) |
“規程管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)

(出所:就業規則ナビ公式Webサイト)
同社の勤怠管理システム「KING OF TIME」の導入を効率化する士業向け支援ツール。アンケートに回答するだけで「KING OF TIME勤怠管理 推奨設定ガイド」を作成できるのが強み。作成したガイドに沿って作業を進めれば、専門知識がなくても顧問先の社内ルールを反映したシステム設定が可能だ。
就業規則の本則、給与規程、育児介護休業規程など16の規程に加え、フレックスタイム制や育児・介護休業に関する協定書など11の労使協定書の作成、雇用契約書の作成までを一貫してサポート。原則ルールをはじめ、1カ月/1年変形、フレックスタイム制といった変形労働時間制や、割増賃金を含む多様な給与計算パターンにも柔軟に対応できる。その他、条文の追加・削除時における条番号の自動修正や、過去の改定履歴の確認、顧問先ごとの文書管理なども備えている。

(出所:スマート規程管理 by LAWGUE公式Webサイト)
社内規程の作成・管理・編集業務を一元化するクラウド型規程管理サービス。新日本法規出版が提供する規程や、過去に作成した規程の条項検索・確認、AIによる条番号の自動補正や表記揺れの検出機能で文章作成時間を短縮できる。過去に作成した条項の検索、解説文の確認、複数人での同時レビューといった、かゆいところに手が届く機能が多数揃う。
コメントごとバージョン保存できるので、「改訂の経緯」「顧客からの指摘」といったナレッジを、資産として蓄積することも可能。

(出所:規程管理システム PSR社労士版公式Webサイト)
各種規定をクラウド上で一元管理し、編集・改訂作業を行うことができる、社労士向け規程管理システム。5企業までの顧問先を登録でき、1社ごとに6規程登録が可能。各企業それぞれの規程をシステム上で一元管理することで、コンサル業務の標準化や業務効率化につながる。
社会保険労務士事務所を母体とし、人事労務業務に関するノウハウが豊富なブレインコンサルティングオフィスの提供ソフトであるため、一般的な雛形に加えて、「経営戦略型就業規則®」など独自の雛形もそろう。法改正時に改正情報が発信されるアラート機能や、届出書類の提出期限を知らせるメール機能などで業務をサポートする機能も充実。
社内の秩序を統制するために作られる社内規程は、組織の根幹であり、企業文化の形成においても重要な意味を持ちます。また、企業や従業員が互いに不利益を被らないためにも、社内規程の整備が必要です。
とはいえ、規程の作成・管理・運用には大きな負担を伴います。また、法改正に合わせて条項を改訂したり、半期〜1年くらいの周期で定期的に見直したりする必要があるので、一度作ったら終わりではありません。
規程管理システムなら、こうした一連の業務を効率化できます。ただし、システム毎に得意分野や機能が大きく違うので、本記事でご紹介した3つのタイプや比較ポイントを参考に、自社に合ったシステムを選んでみてください。
規程管理システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
“規程管理システム”の 一括資料ダウンロードする(無料)
規程管理に役立つ契約書管理システムの更に詳しい選び方は、こちらの選び方ガイドをご覧ください。
契約書レビュー・管理システムの選び方ガイド(比較表付き)
FRAIM株式会社
AIを活用したクラウド ドキュメント ワークスペース。「欠落条項検索機能」「自動補正機能」など特許技術の優れた編集機能により、契約書だけでなく様々な文書の作成・...
株式会社KiteRa
規程の作成/編集に強みを持つ規程DXサービス。豊富なひな型やAIを活用した規程レビュー機能搭載。規程の作成から周知までを一元化、業務効率化に加え、GRC(ガバナ...
住友電工情報システム株式会社
契約書やISO文書管理、電帳法対応など、様々な用途で活用できる文書管理システム。作成~保管・活用~廃棄までを一元化します。生成AIとの連携により、社内文書の活用...
株式会社オプティム
AIで非定型文書から情報を簡単抽出!手書きにも強いOCRでスキャンファイルもデータ化可能。全文検索・期限通知機能で管理業務を徹底サポート!...
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。
資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。
なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。