サイバー攻撃による情報漏えいに不安を感じている経営者や情報システム担当の方へ。サイバー保険の必要性や選び方、補償範囲や費用感など、検討の手がかりとなる情報をおすすめのサイバー保険を交えながらご紹介します。
サイバー保険とは、サイバー攻撃や情報漏えいといったセキュリティ事故による損害に備えるための保険です。被害者対応にかかる費用や訴訟リスク、事業停止による損失の補償など、主に金銭的な負担を軽減する役割を担います。補償内容は幅広く、保険会社やプランによって異なるため、自社の事業形態や内容に潜むリスクと照らし合わせて選ぶことが重要です。
「サイバー保険なんて、大手企業が加入するものでは?」と考える方は少なくありません。しかし、サイバー攻撃のリスクは、企業規模にかかわらず存在します。
たとえば、近年では、多くの企業でテレワークが普及していますが、その分、ネットワークの脆弱性を突かれやすくなりました。私物PCや未更新の自宅ルーター、フリーWi-Fiを経由してマルウェアを埋め込まれるケースなどが典型です。実際大手企業に限らず、セキュリティ対策が手薄な中小企業が標的となるケースが年々増加傾向にあります。
また、2022年の個人情報保護法改正により、企業規模を問わず、情報漏洩えいを起こした場合、「個人情報保護委員会への報告」と「本人への通知」が義務化されるなど、企業側の責任が重くなりました。対応の遅れや不備があった場合、企業評価や信頼を失うリスクも高まっており、事故が発生すれば調査費や被害者対応、業務停止に伴う売上損失が同時多発的に発生します。資金余力の小さい中小企業では、経営の継続に関わるリスクとなり得ます。
こうした事態に備える有効な選択肢のひとつとして考えられるのがサイバー保険です。
2020年時点でサイバー保険に加入していた企業は全体のわずか7.8%でしたが(※1)、2024年の調査では約10%にまで高まっています(※2)。攻撃の巧妙化や情報漏えいリスクの深刻化を背景に、以前よりも「備える意識」が広がっています。企業規模を問わず、事業継続生や自社の信用と存続を支える手段として、サイバー保険を選択肢に含めておくことが重要になってきています。
※1 出典:一般社団法人 日本損害保険協会「企業のサイバーリスク意識調査(2020年)」
※2 出典:一般社団法人 日本損害保険協会「中小企業におけるリスク意識・対策実態調査 2024」
サイバー保険では主に、以下のような事故が補償対象となります(契約内容によって異なる)。
また、第三者の攻撃だけでなく、
といった過失による事故も契約条件に応じて補償対象となることがあります。
本記事では、サイバー事故の傾向、実際に補償されるケースの例も交えながら、サイバー保険の基本と選び方を解説します。
続いて、事故が起こった際に「どこまで補償してもらえるのか」、サイバー保険の主な補償内容について解説します。
まず押さえておきたいのが、ほとんどのサイバー保険契約に共通して含まれている基本的な補償内容です。大きく分けて以下の2つに分類できます。
情報漏えいやシステム停止などにより、取引先や顧客に生じた損害に対して、企業が賠償責任を負った場合の損害額を補償するものです。たとえば、以下のようなものが挙げられます。
判例によっては数千万円単位の賠償責任が発生することもあるため、企業の財務リスクを軽減するうえで重要な補償です。
サイバー事故が発生した際の初動対応や事後対応にかかる費用です。たとえば、以下のようなものが挙げられます。
中には、情報が漏えいした「可能性がある段階」から補償の対象となる保険もあるため、事後の補償だけでなく、初動対応のスピードと質を高める上でも有用です。
次にオプションにより補償内容が分かれるものを確認しましょう。
サイバー攻撃などによりシステムや業務が停止し、利益の損失や営業継続のために発生した費用を補償するオプションです。たとえば、製造工場のサーバーが不正アクセスを受けたことで、生産ラインが一時停止し、販売機会を失ったといったケースが該当します。被害の「間接的な損失」までカバーできる点で、製造業やEC事業者にとっては特に重要な補償です。
サイバー攻撃が原因で、第三者に身体的・物的損害を与えた場合の賠償責任や対応費用を補償するオプションです。たとえば、サイバー攻撃によりビルの防災設備(スプリンクラーやシャッター)が誤作動したことで、オフィス内にいた人や設備に損害が発生した場合などが想定されます。近年はIoT化された設備が増えており、物理的な影響が無視できなくなっていることから、注目されている補償領域の一つです。
サイバー保険の中には、保険料を抑えたい企業向けに、リスクと補償対象を限定したプランも用意されています。よくあるのが、情報漏えい(またはその可能性)によって生じた損害のみを対象とする限定型プランです。
たとえば、情報漏えいに関連する通知費用や取引先への賠償金などは補償される一方、売上損失や営業停止による逸失利益など、自社側の経済的損害は補償対象外となります。こうしたプランを選ぶ場合は、自社が抱えるサイバーリスクの種類や深刻度を的確に見極めた上で、必要な補償範囲を慎重に検討することが重要です。
サイバー保険では、実際に事故が起こった際、「どの程度補償されるのか」、中小企業の事例をもとに解説します(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の「サイバーセキュリティ保険」の事例を参照)。
このケースでは、サイバー攻撃により個人情報データベースから顧客5万件分の情報が漏えい。自社対応が難しかったため、被害拡大を防ぐために、外部のコンサルタント会社に初動対応を依頼。その結果、以下のような費用が発生しました。
合計9,400万円が必要となりましたが、サイバー保険に加入していたため、「再発防止対策費用」を除いた約8,900万円が補償対象となり、大きな経済的損失を回避することができました。
なお、補償額は保険契約の上限額や自己負担金の有無によって変動するため、事前に内容を確認しておくことが重要です。
続いて、サイバー保険に加入することで得られる具体的なメリットを紹介します。損失補填に限らず、信頼性・対応体制・リスク管理といった多角的な支援が期待できます。
サイバー攻撃・情報漏えいなどによって生じるであろう、その後の膨大な手間暇(機会逸失)や損害賠償・売上減少など、様々な損失に備えることができます。
サイバー保険に加入していることは、顧客・取引先に対して一定のセキュリティ対策を講じていることの客観的な証明となります。特にセキュリティ要件が厳しい企業との取引における信頼性確保に寄与します。
原因調査、記者会見対応、コールセンター設置など、事故発生時の対応において経験豊富な専門家の知見が求められます。こういった支援を付帯したサイバー保険を利用すれば、初動の混乱を抑えつつ的確な対応が可能になります。
サイバー保険の加入にあたっては、サイバー攻撃などに関するリスク評価やセキュリティ対策状況の分析が必要となります。そのため、自社の弱点に気づくよい機会にもなります。副次効果として、事故予防を見据えた対策強化へとつながる点も大きな利点です。
サイバー保険の補償対象外となるケースや加入前に知っておきたい注意点など、主なデメリットについて解説します。
サイバー保険は、あくまで事故が発生した後の損害を補償するものであり、攻撃そのものを防ぐ機能や効果はありません。ゼロリスクは存在しないため、日頃の対策と保険による備えを組み合わせる意識が求められます。
ランサムウェア感染によって発生する調査費用や対応費用は補償の対象になりますが、攻撃者から要求される金銭(いわゆる「身代金」)の支払いについては、補償対象外とされるのが一般的です。
サイバー保険は、基本的にサイバー攻撃や情報漏えいなどに起因する損害に限定して補償されます。地震や噴火などの自然災害によるシステム障害やデータ損失については、補償の対象外となるケースがほとんどです。
以下のような事案は、原則としてサイバー保険の補償対象外です。
一部の保険商品では、これらも補償対象とする特約が付帯できる場合がありますが、補償内容の詳細は約款や補償条件を必ず確認することが重要です。
サイバー保険の保険料は一律ではなく、企業ごとの条件に応じて個別に算出されるのが一般的です。企業の規模や業種、サイバーリスクの程度によって、保険料は年額で数十万円から、場合によっては数百万円にのぼることもあります。まずは自社の業務内容や対策状況に照らし合わせ、どの程度の補償が必要かを整理することが、検討の第一歩となります。
保険料は業種、従業員数、売上高、セキュリティ対策の内容、希望する補償額、免責金額(自己負担額)といった複数の要素をもとに算出されます。
セキュリティ体制が十分に整っている企業は、リスクが低いと判断されて保険料が抑えられる傾向がある一方、対策が不十分な場合にはリスクが高いとして保険料が高くなることもあります。正確な金額を知るには、保険会社による審査を受けた上で見積もりを取る必要があります。その場合、自社の対策状況を事前に確認・強化して臨むことが重要です。
事前に取り組める対策としては、まず社内の全端末・サーバーを棚卸し、更新未適用端末があれば即時に更新しましょう。更に外部ベンダーに脆弱性診断を依頼し、レポートを取得しておくと自社のセキュリティ課題を明確化できます。レポート結果と改善計画をISMS規程に反映した資料にまとめてから保険会社へ見積もりを依頼する流れにすれば、サイバー保険の審査をスムーズに進めやすいです。
サイバー保険は形態によって以下の2つに分かれます。
選び方としては、自社のセキュリティ対策が万全なら1の単体契約、そうでない場合は2のセキュリティ対策とセットで提供されているタイプがおすすめです。
ここでは、それぞれの特徴と具体例、どんな企業に向いているかを紹介します。
損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上などの損害保険会社が提供する単体契約型のサイバー保険は、企業の業種や規模、希望する補償内容に応じて柔軟に設計できるのが特徴です。
既に一定レベルのセキュリティ対策を導入している企業に適しており、保険料を抑えつつも必要な補償を確保したい場合に有効です。また、契約時にセキュリティ状況のヒアリングが入ることが一般的で、場合によっては保険料の割引を受けられるケースもあるため自社の体制を見直すきっかけにもなります。より細かな補償内容のカスタマイズを重視したい企業向けの選択肢です。
セキュリティ対策とサイバー保険をパッケージで提供するセット型は、特にIT部門やセキュリティ専門の部署を持っていない中小企業に向いています。このセット型は、更に以下の2つの特徴に分けられます。
保険加入の前段階として脆弱性診断が含まれていることもあり、自社のセキュリティの甘い部分を事前に把握しやすいのが特徴です。可視化された課題に対策を講じることで、事故の予防と補償の両面に備えることができます。
たとえば、NTTドコモソリューションズ株式会社の「サイバー保険付き脆弱性診断サービス」では、ネットワーク、サーバー構成、Webアプリ、スマホアプリの4種の脆弱性診断メニューを提供しており、サイバー保険加入とあわせて自社のセキュリティ体制全体を見直す契機にもなります。
サイバー保険に加えて、PC・サーバーなどのエンドポイントを常時監視するSOC(Security Operation Center)、いざという時に端末におけるウイルスの被害拡大を予防するEDR(Endpoint Detection and Response)など、セキュリティ対策が組み込まれているタイプです。
万が一の際も原因調査や復旧までを一貫して支援。初動対応が標準化されているため事故時の混乱を抑えやすいのも特徴です。調査費用や再発防止策なども補償に含まれる場合があるため、対策と補償を同時に整えたい企業向けの選択肢といえるでしょう。
たとえば、株式会社アクトの「データお守り隊」では、中小企業を対象に端末の常時監視といざという時の原因調査・復旧等とサイバー保険が一体となったセキュリティ対策サービスを提供。サイバー事故対応の専門家による支援やサポート体制も充実しており、自社のセキュリティ体制に課題を感じている企業におすすめです。
サイバー保険を選ぶ際には、補償内容や適用範囲など、いくつか確認しておきたい比較ポイントがあります。ここでは、代表的な項目を取り上げ、それぞれのチェックポイントを整理します。
国内での賠償事故にはどの保険も対応していますが、海外の取引先や顧客への賠償は、補償対象外となるケースも珍しくあります。プランや保険種別によって対応範囲が異なるため、グローバルに事業展開している企業は、加入前に海外対応の有無を必ず確認しておきましょう。
たとえば、東京海上日動火災保険株式会社の「サイバーリスク保険」では、海外の損害賠償請求も補償対象としており、海外事業展開における万一のリスクにも備えられます。
サイバー攻撃を受けた際、原因や被害範囲を特定するデジタル・フォレンジッ調査は非常に重要ですが、自社に知見がない場合は外部の支援が欠かせません。「専門的な知識・技術がない」となると信頼できる外注先を探すだけでも一苦労です。その場合は、フォレンジックに対応したサイバー保険を選ぶことも重要なポイントとなります。
たとえば、AIG損害保険株式会社の「サイバーリスク保険」では、デジタル・フォレンジックに対応する特約プランも提供しています。
サイバー保険の中には、攻撃が発生する前の「おそれ」の段階における調査費用まで補償に含むものもあります。被害拡大を防ぐ手段となるのはもちろん、中には実際に事故が発生した場合にはコールセンターの設置費用や、ネット上での風評被害・炎上対応にかかる費用などが補償されるプランも。セキュリティ対策に重きを置く場合は、こういったサポートまで含まれているかも、比較時の重要な要素といえるでしょう。
たとえば、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の「サイバーセキュリティ保険」では、漏えいが明らかにはなっていない段階からも補償対象に含めるプランを提供しています。

(出所:サイバーリスク保険公式Webサイト)
サイバーリスクに起因して発生し得る各種損害を包括的に補償するサイバー保険。サイバー攻撃による「おそれ」の段階から対応費用を補償し、システム損傷時の修理費用や再発防止費用も対象。海外での損害賠償請求や、システム中断による利益損失・営業継続費用の補償も可能。サイバー攻撃による対人・対物事故への補償もオプションで対応。更に、24時間365日対応の緊急時ホットラインや、リスク診断・モニタリングサービスなど、平時からのリスク軽減を支援。

(出所:サイバー保険公式Webサイト)
包括的な補償と平時からの支援体制を備えたサイバー保険。サイバー攻撃の「おそれ」がある段階から補償対象となり、被害範囲調査、謝罪対応、再発防止までを一貫で支援。従業員による意図的な情報漏えいや内部不正にも対応する特約があり、人的要因への備えも強化。緊急時には専任スタッフが対応する「緊急時サポート総合サービス」を自動付帯。セキュリティ対策状況に応じて最大約60%の保険料割引あり。近年では中小企業での契約が増加している。

(出所:サイバープロテクター公式Webサイト)
内部起因、外部起因問わず、手厚い補償を備えたサイバー保険。賠償損害、事故対応費用、利益損害、システム復旧費用までを幅広く補償。予算や補償範囲に合わせて3つのプランが用意されており、「ワイドプラン」なら海外での賠償請求にも対応。事故時には専門事業者の紹介や24時間365日対応の専用コールセンターが支援。25項目に及ぶ情報管理体制の診断結果に応じて最大60%の保険料が割引あり。

(出所:サイバーセキュリティ保険公式Webサイト)
事故対応費用から賠償責任、利益損害補償までを幅広くカバー。被害発生時のコールセンター設置費用や記者会見費用、風評被害対応費用も補償。情報漏えいの「おそれ」の段階から補償が適用され、初動対応を支援する24時間365日対応の緊急サポート窓口も設置。原因究明・被害範囲特定のためのフォレンジック調査やデータ復旧にかかる専門業者の手配も可能。セキュリティ対策状況に応じた保険料割引制度も導入。

(出所:サイバーリスク保険公式Webサイト)
サイバー攻撃による情報漏えいや業務停止、サイバー犯罪による金銭損失までを幅広くカバー。盗難や紛失のほか、従業員による故意の持ち出しによる情報漏えいも補償。また、リモートワーク中の私用デバイス使用による事故や、取引先への被害拡大などのリスクにも対応。デジタル・フォレンジック費用や危機管理コンサルティング費用、コールセンター設置費用など、初動対応に必要な費用も補償。「ワイドプラン」なら海外での損害賠償請求にも対応。

(出所:サイバー保険付き脆弱性診断サービス公式Webサイト)
脆弱性診断も備えたサイバー保険。ネットワーク、サーバー構成、Webアプリ、スマホアプリの4種の診断メニューを提供し、診断契約額が80万円以上で最大1,000万円のサイバー保険が自動付帯される。補償範囲には、損害賠償金、事故対応費用、システム復旧費用、再発防止費用などが含まれ、診断対象システムに起因する事故に対応。年間約690システムの診断実績を持ち、情報処理安全確保支援士やCISSPなどの有資格者が診断を担当。報告書には脆弱性の詳細や再現方法を明記し、対策後の再診断に対応してくれるのも心強い。
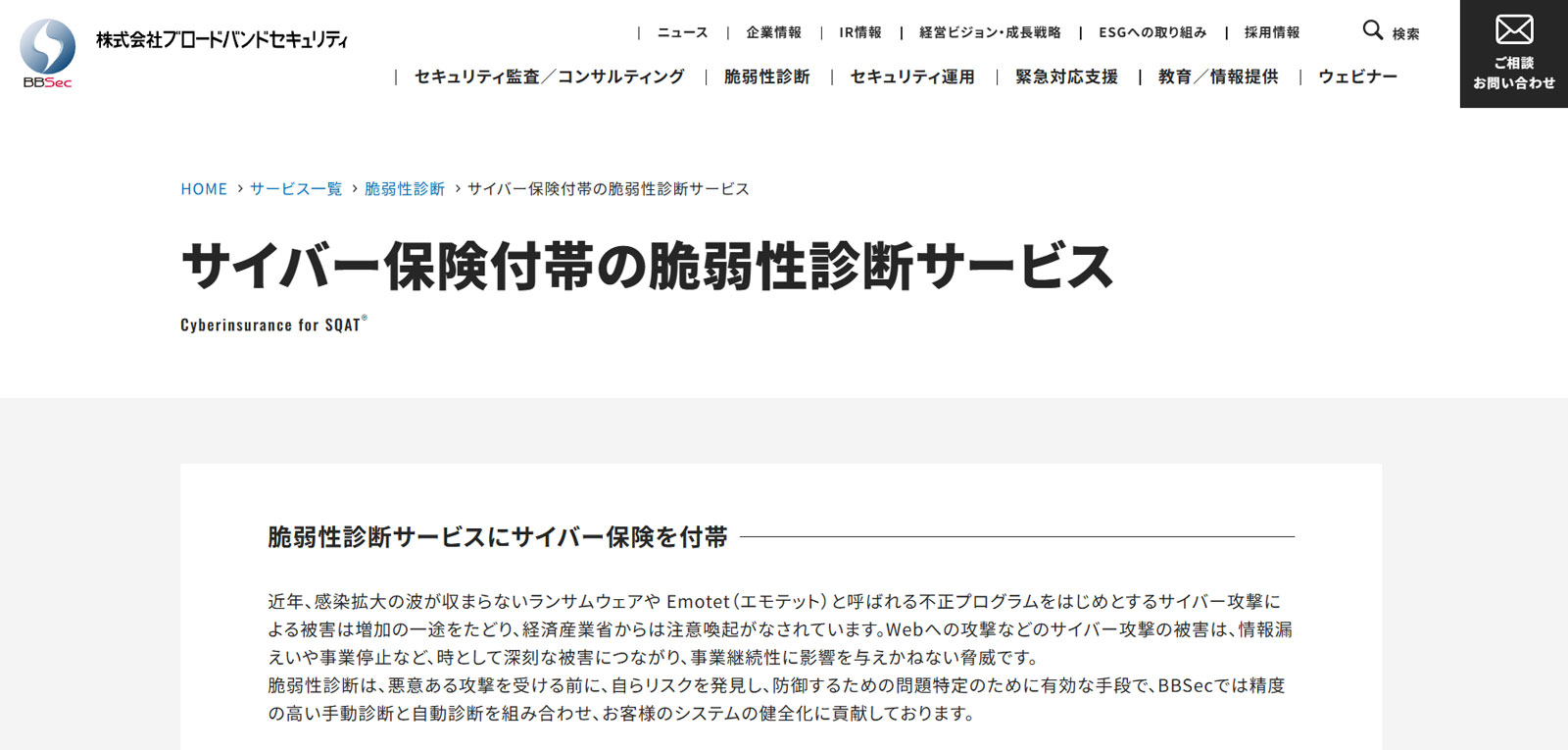
(出所:サイバー保険付帯の脆弱性診断サービス公式Webサイト)
包括的なセキュリティ診断と自動付帯のサイバー保険を組み合わせた統合型サービス。Webアプリケーション、ネットワーク、スマホアプリ、IoT機器、ソースコードなど多岐にわたる診断対象をカバーし、精度の高い手動診断と自動診断の組み合わせによる高品質な脆弱性検出を実現。契約日から1年間、最大1,000万円までの補償が提供され、事故発生時の賠償損害や初動対応費用をカバー。クレジットカード情報漏えい事故調査機関(PFI)としての実績を持ち、金融機関や官公庁を含む幅広い業界での導入実績を持つ。

(出所:Carbon Black SOCサービス付帯 サイバー保険公式Webサイト)
Carbon Black SOCサービスと連携したサイバー保険。VMware Carbon Blackによるエンドポイント監視とSOCによる24時間体制のセキュリティ監視を提供。新規導入企業には1年間の無償サイバー保険を付帯し、賠償補償500万円、事故対応費用200万円を上限に補償。保険単体での契約は不可で、SOCサービスの導入が必須。示談交渉サービスは提供されないが、賠償問題の解決に向けた相談対応が可能。

(出所:データお守り隊公式Webサイト)
中小企業を対象としたEDR/SOC一体型のサイバーセキュリティ対策サービス。EDRによるマルウェアの早期検知、SOCによる24時間365日の監視と脅威解析に加え、サイバー保険を自動付帯。初動対応やデジタル・フォレンジックなど、インシデント対応時に突発的に発生する各種コストも補償。インシデント対応の専門家による支援や、メール・チャットでの相談体制など、初動から復旧までをサポート。1台1,000円から加入できるなど、費用もリーズナブル。
サイバー攻撃の巧妙化と情報漏えいリスクの高まりにより、企業の規模を問わず"もしも"への備えが求められる時代を迎えています。サイバー保険は、経済的損失への補償だけでなく、初動対応や信頼回復の支援も担う、重要なリスクマネジメント手段です。近年では、中小企業にもその必要性が高まっています。
その提供形態は大きく分けて以下の2つです。
サイバー保険を選ぶ場合は、自社の業種や事業規模、現在のセキュリティ対策の状況を整理したうえで、補償内容やサポート体制を比較することが肝心です。特に自社だけで事故対応を完結できない場合は、初動支援や再発防止まで視野に入れたサービスを選ぶことで、より実効性のある備えとなります。費用面だけにとらわれず、将来のリスクに対してどこまで対応できるかを軸に、慎重に検討しましょう。
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
パスワード再設定依頼の自動メールを送信しました。
メール文のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがあった場合がございます。
お手数おかけしますが、再度ご入力をお試しください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
サービスの導入検討状況を教えて下さい。
本資料に含まれる企業(社)よりご案内を差し上げる場合があります。
資料ダウンロード用のURLを「asu-s@bluetone.co.jp」よりメールでお送りしています。
なお、まれに迷惑メールフォルダに入る場合があります。届かない場合は上記アドレスまでご連絡ください。